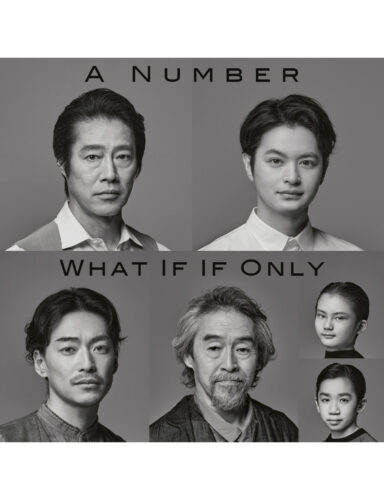スティーブン・スピルバーグ監督の手によって、1961年以来2度目の長編映画化となる『ウエスト・サイド・ストーリー』。(日本では2022年2月11日に公開)1957年にブロードウェイミュージカルとして発表された本作は、現代にも通じる問題が色濃く反映されています。今回は物語に隠されたメッセージを、当時の時代背景とともに紐解きます。
スピルバーグ監督『ウエスト・サイド・ストーリー』を映画館の大スクリーンで観るべき3つの理由
『ロミオとジュリエット』を参考に制作された禁断の恋物語だけれど…。
まず、『ウエスト・サイド・ストーリー』のあらすじを簡単におさらいしましょう。舞台は1950年代のアメリカ・ニューヨークのウエスト・サイド。そこでは、プエルトリコ系移民で構成された「シャークス」と、ヨーロッパ系移民「ジェッツ」という2つの不良グループが対立していました。ある日、シャークスのリーダーを兄に持つ少女マリアは、ジェッツの元リーダー・トニーに出会い、惹かれ合った2人は禁断の恋に落ちます。しかし、2つのグループの対立は激しさを増し、ついにグループ同士の決闘が始まってしまいます。
この恋の結末はみなさんご存知の方も多いかと思います。シェイクスピアの悲劇『ロミオとジュリエット』になぞらえられた本作は、1950年代のアメリカで社会問題になっていた事柄も加味された上で制作されました。次項ではより物語を深堀するため時代背景を紐解きます。
ただの恋物語ではない、ストーリーに込められた人種・貧困などの社会問題への問題提起
1945年に第二次世界大戦が終了。1950年代のアメリカでは、アメリカンドリームや自由を夢見てやってきた移民への人種差別や貧困などの社会問題が深刻化していました。『ウエスト・サイド・ストーリー』内の楽曲「America」でも、アメリカは「自由の国」で「快適に過ごせる」と夢見る女性たちと、「入店拒否される」「靴を磨かされる」といった差別や貧困を憂う男性たちの対比的な掛け合いが見られます。アメリカという国の二面性が描かれている1シーンです。
『ウエスト・サイド・ストーリー』でトニーとマリアの恋を阻むのは、プエルトリコ系移民とヨーロッパ系移民の対立。クリストファー・コロンブスがアメリカ大陸を“発見”して以降、イギリス・スペイン・ポルトガル・ドイツ・スウェーデンといった各国からアメリカに移住。1880年代から始まったユダヤ人の移住や、奴隷としてアフリカ系アメリカ人が連れて来られるなど、世界中から多様な歴史を持つ人々が集まる国となりました。アメリカを舞台に描かれた『ウエスト・サイド・ストーリー』は、異なる立場の者同士が出会い、対立を超えて共存することができるのかというメッセージを表しているといえます。

そしてこのミュージカルが誕生して70年以上経った今でも、問題は解決しておらず分断は広がる一方です。スピルバーグ監督は今回の映画化において「1957年のシャークスとジェッツの分断よりも、私たちが直面している社会の分断の方が深刻であることに、5年をかけた脚本づくりの過程で気づいた。人々の分断は広がり、もはや人種間の隔たりは一部の人の問題ではなくなった」と語り、この問題を改めて提議する映画となっています。

マリア役のレイチェル・ゼグラーを始め、多くのプエルトリコ人家系の役者を起用した本作。キャスト間では多くのディスカッションが交わされた上で、映画製作が行われました。ミュージカル映画の名作中の名作が、現代にリメイクされる意味を思いながら今一度観賞したい作品です。