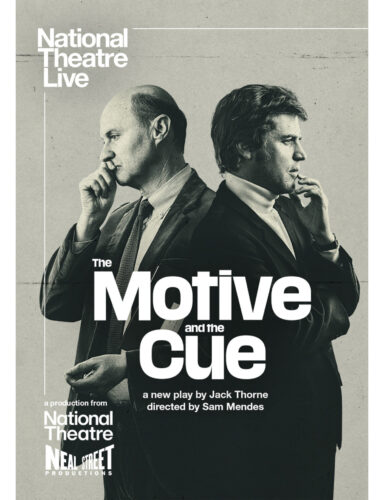成宮寛貴さんが12年ぶりに挑む舞台は、三島由紀夫さんの名作『サド侯爵夫人』。俳優デビューした舞台『滅びかけた人類、その愛の本質とは…』を手がけた宮本亞門さんと25年ぶりに再びタッグを組み、世界で愛される名作に挑みます。
生々しい匂いの中に見える、ピンと張られた細い線

−本作は成宮さんと宮本さんが偶然出会ったことから始まった企画だそうですね。
「まるで運命だったのかなと思うほど、偶然にも海で再会したんです。そこから一緒に食事に行って、“どんなことに興味があるの?”“俳優としてもちろん舞台にも挑戦したいです”といった話をしているうちに、 “あれ、もしかしたら亞門さんとお仕事をご一緒することになるのかな”とふと感じる瞬間があって。その予感が現実になった、そんな感覚があります。全てが自然な流れで実現に向かっていったので、これはもう、やるべき運命なのだなと思っています。進むべき道に、ちゃんと導かれているような感覚があります」
−作品が発表された時、成宮さんが『サド侯爵夫人』をリクエストされたのかなと思ったのですが、宮本亞門さんのご提案だそうですね。成宮さんは亞門さんと話した時、何かリクエストをされたのですか?
「17歳のときに亞門さんと出会ってから、自分の中で根本的な部分は何も変わっていない──そのことは、今回お会いした際にもお伝えしました。もちろん大人になる中で変わったところもありますが、芯の部分はずっと同じだと自分でも感じています。そして、俳優の活動を少しお休みして、このタイミングで戻ってくるとなったとき、きっと何かしら乗り越えなくてはならない“試練”のようなものがあるはずだと思っていました。そうしたお話を亞門さんともした上で、この作品を僕のために選んでくださったのではないかと感じています。亞門さんご自身はきっと断られると思ったとおっしゃっていましたが、僕はむしろこれは自分がやるべきお仕事なんだと自然に思えたんです。とはいえ、この作品を提示されたときは意外でした」
−三島文学に触れてみていかがでしたか。
「僕はこれまで三島さんの作品にほとんど触れたことがなかったのですが、読んでみると、表現の仕方がとても独特で、なんだか生々しい匂いが鮮やかに香ってくる、だけどその中に人間としてどう生きるかという、ピンと張りつめた細い線が何重にも走っている。非常に高い芸術性を感じましたし、これが古典と呼ばれる理由がよく分かりました。
『サド侯爵夫人』は男性が書いた、男性から見た女性像が描かれています。シェイクスピア作品にも通ずるような、男性が抱く女性への憧れ、女性から受ける壮大な愛、そして男性には決して捉えきれない女性の第六感のようなミステリアスな部分というのが色濃く織り込まれている印象がありました。その中のどこに三島さんがいるのだろうと考えながら読む時間が楽しかったですね」
−本作は「サディズム」の語源になったサド侯爵を待ち続ける妻と、5人の女性たちが描かれています。サド侯爵は登場せず、女性たちのみで展開される会話劇というのが特徴的です。
「言葉だけで想像するというのは、とてもセンシュアルですよね。僕自身もサド侯爵は登場してこないということを知りながら読み進めていましたが、彼女たちの会話が交わされている空間にいるようなドキドキ感を持って読みました。きっと観てくださる方も同じような感覚が届くのではないかと思います」
−サド侯爵が登場しないというのは観客としては面白いポイントですが、役者としては見えない人を想って演じるのは難しいのかなとも思いました。
「サド侯爵は物語の後半にかけて、どんどん神格化されていきますよね。そうなると、もはや想像したもの勝ちのようなところがあると感じています。御神体というのものはどう想像しても良いはずなのに、それをみんなが“こうだった”と勝手に語っているだけで、本当の姿がどうなのかは誰にも分からない。そして人によっても見方が違うもので、立ち位置が変われば当然見え方は変わるので、自由に想像してもいいのかなと思っています。今はまだ頭の中で混線しているところもあるのですが、稽古を通じて少しずつ整理し、役としての芯を見つけていきたいと思っています」
青い炎のように静かに熱く燃えるルネを純真に

−成宮さんはサド侯爵を待ち続ける貞淑な妻・ルネ夫人を演じます。ルネはどんな人物に映っていますか。
「18世紀のフランスで、男性、そして時代に翻弄されてしまう中で、夫を愛すると決め、最後まで貫き通した女性です。爆発的なエネルギーではなく、青い光のように、内側だけの高い温度で燃えているような強さを感じています。そして貞淑のお手本のような人。お芝居としてもミニマムに受け止めていくということを一回突き詰めてやっても良いのかなと思っていますし、ラストにかけては、人物の中に潜む微かな意地悪さや陰影をにじませるよう意識して演じても良いのかなと思っています。皆さんと一緒にお芝居をしていく中で見えてくるものもあるので、とても楽しみです」
−劇中では、ルネの若い頃から歳を重ねた姿まで、長い期間を演じますよね。
「でも彼女は歳を重ねても変わらないんですよね。彼女は1人だけ変わらない。最後に相手が変わったことで、自分自身が変わる。そのけじめと言いますか、決めたらこう、という力強さを凄く感じています。自分もそのような生き方が出来たら良いなと思う、尊敬すべき部分が数多くある方です」
−現代的な感覚からすると、現実味のない人物にも感じる部分もあるかもしれません。
「その人物にリアリティを持たせるためには、まず彼女の内側にある真っ直ぐで純真な部分を自分の中に持っていなければいけないと思っています。おそらく我々は、彼女よりも少しだけ器用に生きてしまうことがある。でも彼女は生き方を変えたくても変えられないし、変え方も分からない。信じるものをただ信じて突き進んでしまう──その不器用さやひたむきさを、芝居の中で丁寧に立ち上げていきたいですね。実は僕自身もそういうタイプなので、そのリアリティを舞台上にしっかりと宿せるよう、頑張りたいです」
−本作の何が一番大変そうだと思われますか。
「もちろん台詞量は非常に多いですし、僕たちが日常的に使っている口語とは違うレトリックが随所に散りばめられているので、それを観客の皆さんに分かりやすく届けるという課題もあります。おそらくセットが過度に装飾されたものではないと思うので、独白のように聞こえる台詞をどう成立させるか、そのあたりは稽古の中でじっくり探っていく必要があると感じています。それに方向性の異なる女性たちがそれぞれの視点で思いを語る場面が多い分、主観と俯瞰の芝居をどう切り替えるか、相手の“そう来たか”に対して“じゃあ自分はこう行こう”と選択していく、その連続になるだろうと思うんです。そのプロセスが楽しみです。最終的に何を選び取るかというのは、その人のセンスだと思いますし、この作品に集まっているキャストはそのセンスが抜群な方ばかりだと思います。もしかしたら、僕が一番の劣等生かもしれないです」
信じていたものが覆る時代に、届けたい

−本作は18世紀のフランスの激動の時代を描いています。三島由紀夫さんも戦後という日本が大きく変わる時代に生きていたからこそ、サド侯爵という題材に惹かれたのかもしれません。
「我々が最近経験したのは、コロナ禍や大地震ですね。トランプ大統領の発言によって株価が大きく動いたり、日本では女性初の総理大臣が誕生したりということもあります。どの時代にもそうだと思うのですが、劇中の台詞にもあるように、信じていたものや正しいと思っていたことが悪になったり、今まであった制度がなくなったり、いつ価値がなくなるか分からないというのはあると思います。そのようなことも含めて、『サド侯爵夫人』は凄く良いタイミングで参加させて頂けていると感じています」
−宮本亞門さんとは本作について既にお話しされていますか?
「亞門さんとはいつもプライベートで仲良くさせて頂いていたので、今はあえて連絡をとっていません。僕だけが仲が良いとずるいじゃないですか(笑)。お友達ではなく、演出家と俳優という関係に戻るために、今はあえて距離を置いています」
−宮本亞門さんの演出に期待されることは?
「凛とした空気をまとった、非常にかっこいい舞台になるのではないかと思っています。そして亞門さんは三島さんの大ファンだし、また数多く手がけてこられた方でもあるので、ぜひいろいろとご指導いただければと感じています。17歳の頃以来のご一緒になるのですが、亞門さんが“心中するつもりで臨む”とおっしゃっていたので、僕も同じ覚悟で、しっかりと立ち向かいたいと思っています」
−本作を楽しみに待っている観客へメッセージをお願いします。
「お久しぶりです。演劇をフォーカスしているメディアに出ると、また俳優としての自分に立ち返ったような実感が湧いてきます。今回復帰後初の舞台が、三島由紀夫さんの『サド侯爵夫人』になりました。幾つもの試練を経て、作品として胸を張って観ていただけるところまで高めていきたいと思っています。三島由紀夫さんを知らない方でも、僕たちが出ていることで楽しんでもらえると思います。時代は違いますが、今の時代とリンクして感じるものもたくさんあります。舞台が初めての方にとっては、少し敷居が高く映るかもしれませんが(笑)、僕たちの姿をぜひ観に来てください」
舞台『サド侯爵夫人』は2026年1月8日(木)から2月1日(日)まで東京・紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA、2月5日(木)から8日(日)まで大阪・森ノ宮ピロティホール、2月13日(金)・14日(土)に愛知・穂の国とよはし芸術劇場PLAT 主ホール、2月17日(火)・18日(水)に福岡・福岡市民ホール中ホールで上演。
作:三島由紀夫 演出:宮本亞門
出演:成宮寛貴、東出昌大、三浦涼介、大鶴佐助、首藤康之、加藤雅也
公式HPはこちら


とても気さくにお話ししてくださった成宮さん。『サド侯爵夫人』という大きな宿命にも立ち向かい、乗り越えていくしなやかな強さを感じました。