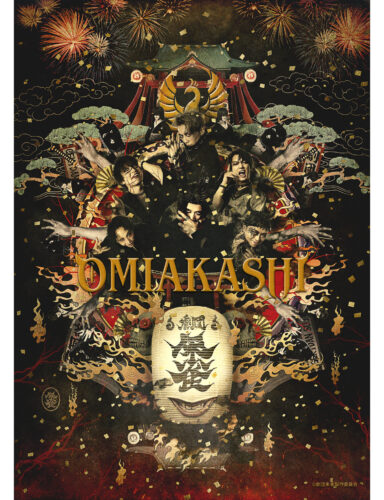2026年9月に上村聡史さんを演劇芸術監督に迎え、開幕する新国立劇場2026/2027シーズン。芸術監督としての指針と共に、2026/2027シーズンの演劇ラインナップ作品が語られました。
『物語の更新(アップデート)』を目標に

「めまぐるしく変化を遂げる文明の進歩や、時計の針を逆戻ししたかのような世界情勢、そして少子高齢化・人口減少の日本。世界総体を見ても今、社会の転換のフェーズの真っ只中にあると思います。そうした中にある人の生活感覚というものをしっかり捉えながら、国立劇場の役割を果たしていければと思っております。
演劇は紀元前のギリシャ悲劇に始まり、中世を経てルネサンス期にはシェイクスピアを中心に大きな花を咲かせました。その後、社会の在り様をリアリズムの視点で捉えた近代演劇、そして表現の可能性を多彩な劇言語で広げてきた現代演劇と、その時代と呼吸しながら変化・発展を遂げてきました。
今、転換の時期にあるという意味においても、演劇がさらに前進する必然性があると言っても過言ではないと思います。総合芸術である演劇は、脚本以上に、表現者の発する声や表現そのものが物語性を持ちます。時代の変化の中で、表現そのものがもう一つ前進する、演劇のさらなる進化、表現も含めた『物語の更新(アップデート)』を目指していきたいと思います」と語った上村さん。
プログラムの構成にあたっては、以下の4つの視点を掲げました。
- 現代的、国際的、批評的:書き下ろし新作、古典・近代戯曲などの上演を問わず、どの演目においても、問題提起すべき事象を意識した現代性、グローバルスタンダードを見つめた国際性、演劇が社会における役割を果たす批評性を踏まえた作品づくりを目指す
- クロスオーバー、他ジャンル(音楽、ダンス、文芸、漫画、映像など)とのつながり:これからの新しい表現方法を展開していくため、他ジャンルとの交流を積極的に図った作品づくりを目指す
- 新しい才能との出会い:次代の演劇の発展のため、出演者・スタッフともに、新しい才能の登用と交流できる場づくりを行う
- 消費で終わらないパフォーマンス:舞台空間を構成する素材・資源等の長期活用や、再演作品の上演形態を工夫し、消費で終わらない舞台芸術を目指す

シーズン開幕を飾るのは、上村演出で贈る『巨匠とマルガリータ』
2026年11月、シーズンオープニング作品として中劇場で上演されるのは、ミハイル・ブルガーコフ原作の『巨匠とマルガリータ』。上村さんがブルガーコフ作品の演出を手掛けるのは、第32回読売演劇大賞優秀作品賞を受賞した『白衛軍 The White Guard』に次いで2度目となります。
ブルガーコフが1929年〜40年にかけて執筆した長編小説『巨匠とマルガリータ』は当時ソ連当局によって体制批判とみなされ、検閲版として出版にこぎつけたのは作家の死後26年が経った66年、完全版が出版されたのは73年でした。
上村さんは本作の「原稿は燃えない」という一節を紹介し、「芸術の価値、芸術の継続性、芸術の創造性、そしてそこには社会における人の善と悪といった存在意義が深く結びついているテーマの作品になります。
『白衛軍』より幻想的な世界観になっていますが、抑圧や権力的な構造を批評的に捉えたブルガーコフの眼差しは変わらず、国益優先化しつつある今の世界において、過去・現在・未来を捉えた『巨匠とマルガリータ』の世界観は、意味のある現代上演だと考えています。過去に敬意を払い、今の視点でそれを語り、未来へ繋げるといった私の指針と重なる内容だと思っております」と思いを語りました。
今回は、英国のナショナル・シアターや王立演劇学校(RADA)で活躍したエドワード・ケンプさんにより、主人公である「巨匠」を小説家から劇作家に翻案した戯曲版(2004年初演)にて上演。キャストに成河さん、花乃まりあさん、大鷹明良さん、篠井英介さんらを迎えます。

<ストーリー>
舞台は1930年代のモスクワ。文学界は官僚主義と検閲にがんじがらめ。そんな中、劇作家である、通称「巨匠」は、キリストの処刑を決めたローマ総督・ピラトを題材にした野心的な作品を書き上げる。しかし、その作品は体制に受け入れられず、激しい批判にさらされ、絶望の淵に突き落とされた結果、彼は自分の原稿を焼き払い、精神病院へと姿を消してしまう。一方、巨匠には愛する女性、マルガリータがいた。彼女は美しく聡明で、巨匠の才能を誰よりも信じていた。巨匠がいなくなり、絶望的な日々を送るマルガリータの前に、突如として奇妙な外国人ヴォランドとその取り巻きたちが現れる。ヴォランドはモスクワの街で様々な騒動を引き起こしながら、市民たちの本性を試そうとしていた。マルガリータは、唯一の願い”愛する巨匠と再び会うこと”を叶えてもらうためにヴォランドの取引に応じる。ヴォランドの目的、巨匠の運命、そしてマルガリータの愛の行方は一体どうなるのか?モスクワの日常と幻想的な世界が交錯する中で、人間の善と悪、愛と信仰、そして芸術の真価を深く問いかける壮大な物語。
藤子・F・不二雄の傑作SF短編を初の舞台化『ミノタウロスの皿』

2026年12月に小劇場で上演されるのは、さまざまなジャンルとのクロスオーバーを目指す『ミノタウロスの皿』。人類が食用の家畜であるイノックス星を舞台に繰り広げられる藤子・F・不二雄さんの短編SF漫画を、ダンスカンパニーCHAiroiPLIN主宰のスズキ拓朗さんによる脚色・振付・演出によって上演します。
また本公演は4歳以上の未就学児から楽しめる、幅広い観客層に向けてのクリエーションとなります。
<ストーリー>
宇宙空間で制御不能に陥った宇宙船。乗組員一名を残しイノックス星に不時着する。
そこには酸素も原始的な文明も存在した。幸い人類もいて、乗組員は手厚い歓迎と看護を受ける。その看護してくれた人類の中に、ミノアという名の少女がいた。乗組員はいつしかミノアに好意を抱き、仲良くなるのだが、実はイノックス星は、地球で云うところの、牛(イノックス星ではズン類と呼ばれている)が支配階級で、人類(イノックス星ではウスと呼ばれている)はその家畜だったのだ。
あらためて支配階級のズン類の歓迎を受ける乗組員。だが、驚くべき事実を告げられる。それは、ミノアは年に一度のミノタウロスの大祭で大皿に乗せられて、ズン類の食用に供される家畜だったという事実。しかも、それはイノックス星では最高の名誉で、そのためにウスは存在しているのだ、と。
やがて、大祭の日がやってくる。乗組員は、ある決意をもって会場に向かう……。
「現代的、国際的、批評的」をテーマに掲げた『ナハトラント~ずっと夜の国~』
2027年3月に小劇場で上演されるのは、ドイツの現代作家マリウス・フォン・マイエンブルクの『ナハトラント~ずっと夜の国~』(日本初演)。ナチス・ドイツというデリケートで重いテーマを、 現代を生きる家族の日常にブラックユーモアをもって落とし込んだ力作です。
「先進国を中心に巻き上がっている非グローバリズムや排外主義といった右派ポピュリズムを風刺した家族劇になっています」と、上村さん。
翻訳を手がけるのは、ドイツ在住で、数多くのドイツ作品の翻訳を手掛けている長田紫乃さん。演出は、約4年間にわたる「こつこつプロジェクト」を経て25年に上演された『夜の道づれ』で、作品を深く掘り起こし戯曲に丁寧に向き合った柳沼昭徳さんが担います。
<ストーリー>
闘病の末に父親が亡くなって2週間後、ニコラとフィリップは遺品整理のため実家へ集まる。特に価値のあるものは見つからない中、ニコラの夫・ファービアンが、屋根裏で小さな水彩画を見つけ、フィリップの妻・ユーディットが、その絵の署名が「A. Hitler」(アドルフ・ヒトラー)ではないかと言い出す。ニコラとフィリップは、それまで気にも留めていなかった絵に急に執着しだし、鑑定士・エファマリアを呼ぶ。ナチスとの関わりが証明できれば高額で売れるだろうと聞いた二人は必死に証拠を探しだすが、ユダヤ系のユーディットはそれに激しく反発、絵の真贋をめぐって関係はどんどん険悪になっていく。そんな中、購入を希望する画商・カールまで現れ……。
“金融取引”をテーマに世界経済から垣間見える“分断”をサスペンスフルに描く『見えざる手』
2027年4月に小劇場で上演されるのは、ピュリッツァー賞を受賞したアメリカの劇作家アヤド・アクタルによる『見えざる手』。オビー賞(劇作部門)、ジョン・ガスナー劇作家賞を受賞、16年イブニング・スタンダード賞および、17年ローレンス・オリヴィエ賞にノミネートされるなど、英米で多くの賞賛を浴びた作品が日本初演を迎えます。
経済学の父、アダム・スミスが唱えた「見えざる手」。各個人の利益の追求が、社会全体の利益や調和をもたらすだけでなく、皮肉にも信仰や倫理までをも飲み込んでいく様が描かれます。演出は上村聡史さんです。
<ストーリー>
パキスタンのとある監禁部屋。
アメリカ人銀行員のニック・ブライトは、上司と間違われイスラム系テロ組織に誘拐される。要求された身代金は1,000万ドル。政府も銀行も動かない孤立無援の中で、彼は組織にある”取引”を持ちかける──それは、自らの金融知識を使って市場で資金を稼ぎ出すことだった。
ニックと対峙するのは、理想に燃える若き組織員バシール、その手下で監視役のダール、そして組織を率いるイマーム・サリーム。ニックと彼らの間に築かれた金融取引のシステムは、やがて組織に富をもたらすと同時に、個人の信念と人間関係の均衡を崩し、蝕んでいくのだった。
資本の力が信仰を揺るがし、理念が数字に飲み込まれるとき──誰が操る者で、誰が操られる者となるのか?
命と信仰を賭けたマネーゲームの果てに現れる「見えざる手」とは何か、そしてニックは「自由」を取り戻すことができるのか?
男性支配の強い最貧国に生きる女性たちを描く『Ruined 奪われて』
2027年5月に上演されるのは、ピュリッツァー賞を2度受賞した唯一の女性劇作家、リン・ノッテージによる、『Ruined 奪われて』。
本作は、コンゴ内戦下で性暴力を受けた女性たちが、極限状況において、いかにして尊厳を保ち、生き抜いたのかを描いた力作。善悪の二元論では捉えきれない登場人物たちを通し、それでも生きていく女性たちの姿を鮮やかに描き出し、ピュリッツァー賞、オビー賞をはじめ数々の賞を受賞しました。
上村さんは本作について「コンゴ民主共和国における女性の実態に基づくセンセーショナルな物語です。こういった現状がこの同時代にこの世界に本当に起きているといった衝撃を、日本で生きている私達も感じる作品になるでしょう。ですがそれは、同じ世界の住人として決して他人事では済まされない真実だと思います。
男性支配の強い最貧国を舞台に、胸をかきむしられるエピソードがいくつも出てきます。 しかしそういった緊迫感や苦しみや痛みを抱えながらバーを営み、地に足をつけながら、それでも明日を生きていこうとするエネルギッシュでユーモアあふれる女性たちのヒューマンドラマになっています。劇中女性たちとの会話とともに綴られる生バンド演奏も見どころの一つで、作品全体に生命力への尊さが描かれる作品になるかと思います」と語りました。
演出は五戸真理枝さんが手がけ、一部の役については公募オーディションが開催されます。
<ストーリー>
コンゴ民主共和国の内戦が続く中、ママ・ナディは、政府軍、反政府軍や鉱夫が入り乱れる小さな町でバー兼売春宿を営んでいる。ある日、行商人のクリスチャンが、性的暴行で心身に深い傷を負った2人の女性、ソフィとサリーマを連れてくる。ママ・ナディは、金儲けのために彼女たちを雇い入れる一方で、必死に安全を守ろうとする。店では、女性たちが客にサービスを提供しながらも、歌やダンス、ささやかなおしゃべりを通して、わずかな日常と尊厳を取り戻そうとしている。しかし、戦火はバーの内にも迫り、兵士たちの襲撃や暴力が繰り返され、彼女たちは再び傷を負う。
現代日本を舞台に、生と死の「選択」を描く新作『抱擁』
2027年6月に上演されるのは、日本人劇作家・山田佳奈さんによる新作書き下ろし作品『抱擁』。現代日本を舞台に、孤独や孤立が覆う世界でいかに尊厳を持って命を終えることができるのか、生と死をめぐる葛藤を、日本的な視点と国際的な視点を交えながら描かれます。演出も山田さん自身が手がけます。
<ストーリー>
埼玉県の小さなメキシカン食堂。店を畳む決意をした母・英子と娘・真莉は、閉店までの残りわずかな日々を過ごす。真莉は妊娠中だが、夫が行方不明になって一か月が経つ。一方、進行性の難病を患う英子は、スイスでの安楽死を密かに準備していた。食堂には、病院ボランティアの老人・橋本、外国人アルバイトのジャン、派手な中国人女性・典らが集い、それぞれ異なる文化や死生観が交錯していく。
そこに英子の旧友の娘・凪が訪ねてきて、母娘は「生きること」「死を選ぶこと」の意味を突きつけられ、互いの価値観は激しくぶつかり合う。
やがて英子の誕生日、食堂で開かれたささやかなパーティーの中で、真莉は初めての胎動を感じ、母は静かに旅立ちの時を迎える。
希望の兆しに向かって。新プロジェクトで上演する『エンジェルス・イン・アメリカ』

2027年7月に小劇場で上演されるのは、上村さんが2023年に演出したトニー・クシュナーの名作『エンジェルス・イン・アメリカ』。本作は、毎シーズン”共通の舞台美術”で上演し、社会の持続性に伴う資源の有効活用を目指すプロジェクト「グリーン・リバイバル・ラボ」の第一弾作品となります。
1980年代半ばのエイズ禍のニューヨークを舞台に、セクシュアリティ、人種問題、信仰、政治など、アメリカ社会が抱える苦悩や葛藤を浮き彫りにした傑作群像劇。エイズを発症したゲイの青年・プライアーを中心に、人々が懸命に前に進もうとする姿を、天使の登場などファンタジーの要素も織り交ぜながら描きます。
上村さんからは「昨年末には東京高裁における同性婚訴訟において合憲との判決があり、多様性と謳われながらも、日本においてはまだこの議論が必要なのかといった問題を扱うことになりますが、80年代アメリカで共和党政権時代に苦しみ死した先人たちを描いた本作は、社会の未来を願うグリーン・リバイバル・ラボの理念と相似形を描いているように思っております。より一層、希望の兆しを感じるよう、自信を持って皆様にお届けしたい」と語られました。
<ストーリー>
〈第一部〉
1985年ニューヨーク。青年ルイスは同棲中の恋人プライアーからエイズ感染を告白され、自身も感染することへの怯えからプライアーを一人残して逃げてしまう。モルモン教徒で裁判所書記官のジョーは、情緒不安定で薬物依存の妻ハーパーと暮らしている。彼は、師と仰ぐ大物弁護士のロイ・コーンから司法省への栄転を持ちかけられる。やがてハーパーは幻覚の中で夫がゲイであることを告げられ、ロイ・コーンは医者からエイズであると診断されてしまう。職場で出会ったルイスとジョーが交流を深めていく一方で、ルイスに捨てられたプライアーは天使から自分が預言者だと告げられ……。
〈第二部〉
ジョーの母ハンナは、幻覚症状の悪化が著しいハーパーをモルモン教ビジターセンターに招く。一方、入院を余儀なくされたロイ・コーンは、元ドラァグクイーンの看護師ベリーズと出会う。友人としてプライアーの世話をするベリーズは、「プライアーの助けが必要だ」という天使の訪れの顛末を聞かされる。そんな中、進展したかに思えたルイスとジョーの関係にも変化の兆しが見え始める。
劇場に足を運びやすい価格帯のチケット料金を提供する「Theater Day」も
また、新国立劇場で実施されるプロジェクトとして「グリーン・リバイバル・ラボ」のほか、五戸真理枝さんを演出に迎え、劇作家を公募、出演者のフルオーディションを行う「集団創作における新作」、世界各地で話題となっている演劇ムーブメントや日本で生まれる新しい劇言語について、トークイベントやリーディングイベントで探究していく「ドラマクエスト – 物語の探求 -」が実施されます。
さらに、「現在、財団と相談している最中」としながらも、演劇部門の作品において劇場に足を運びやすい価格帯のチケット料金を提供する「Theater Day」についても明かされ、「シーズン中に幾つかの演目で試験的に導入しながら、現場における作り手たちの負担が内容、サービスとクリエーションの理想的な着地点を見定めていきたい。新国立劇場の芸術監督は予算や価格についてその範疇にはありませんが、将来の演劇文化を見据えた時、やはり観劇料金は欠かせない項目になると思っております」と強い思いが語られました。


社会的で国際的。そして7本のうち3本が日本初演、2本が新作。上村さんらしいラインナップにワクワクしました。今この時代に演劇が何を見せるのか。どう『物語の更新(アップデート)』が行われるのか。2026/2027シーズンが楽しみなのはもちろん、今後はシェイクスピア作品やチェーホフ作品での“アップデート”も見てみたいです。