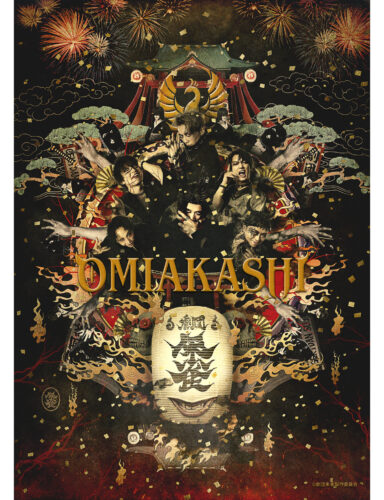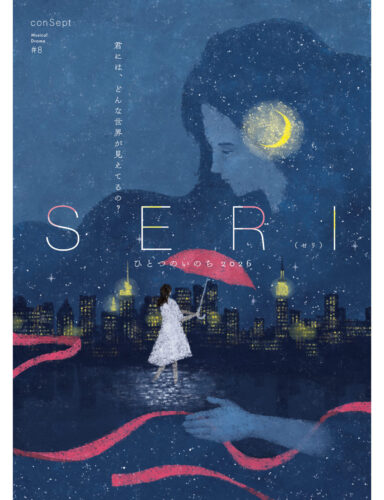2020年12月から、「PARCO劇場オープニング・シリーズ」として上演された舞台『チョコレートドーナツ』。アメリカの映画祭全てにおいて観客賞を受賞した、同名映画に感銘を受けた、演出家・宮本亜門さんが世界初の舞台化を実現しました。
自分らしさを表現すること。愛し、愛されたいと思う者同士がともに過ごせること。平等に与えられるはずの権利を阻む法律と世間の目…観る者に訴えかけるメッセージ性と問題提起の深さに、今、多くの方に観てほしい作品です。
実話に発想を得た、心揺さぶるフィクション
舞台は1979年のアメリカ・カリフォルニア。シンガーを夢見るルディはショーパブダンサーの仕事で生計を立て、家賃の支払いに追われる日々。ある日、ルディの隣人が薬物所持で逮捕され、その息子・マルコは施設へ連れて行かれることに。家に帰ろうと施設を抜け出し、街を彷徨っていたマルコを偶然見つけたルディは彼の運命を不憫に思い、彼を引き取るべく、店で出会った検察官・ポールに相談します。
ルディとポールは親密な仲になり、血の繋がらない3人はやがて一つ屋根の下で生活を始めます。マルコにとって生まれてはじめての「ぼくのおうち」。ダウン症を持つマルコに愛情を注いであげられるのは世界中で自分たちだけ、と確信したルディとポールは、彼を息子のように大切に育てます。ハロウィンにクリスマス、毎晩のベッドサイド・ストーリー。幸せな家族の思い出が少しずつ増えていきました。
しかし、同性カップルであるために、ルディとポールにはマルコの監護権が認められません。愛情で結ばれた3人を引き裂く、法律と差別。「今こそ、法律で世界を変えるチャンス」というルディの言葉を励みに、2人はマルコを取り戻すための裁判に臨みます。彼らが家族として認められる日は来るのでしょうか…?
脚本のジョージ・アーサー・ブルーム氏がかつて出会った、母親に育児放棄された障害を持つ子どもと、家族のように過ごすゲイの男性。彼らが法的な親子関係になろうとした場合に想定される課題を盛り込んだフィクションを構想し、映画『チョコレートドーナツ』が生まれました。
私は堂々と生きていい。祈りを込めるルディの魂の歌声
本作において、ルディがシンガー希望のドラァグダンサーである、という設定は大きな意味を持っています。女装を異常と捉えていた時代にその仕事を堂々とやり抜くルディは、不当な扱いに対して真っ向から反対できる強さを持つ人物。心の奥で堪えた涙を歌声に込め、自分らしく生きる権利を世間に主張していきます。
『チョコレートドーナツ』原題の『Any Day Now』という言葉は、作中でルディが魂を込めて歌い上げるボブ・ディランの名曲『I Shall Be Released』の歌詞を引用したもの。いつの日か、私は解放される。映画でも舞台でも、ルディの自己表現が作品パワーの核になっている本作を象徴するタイトルです。
一方のポールは自分らしさを隠しつつ、正義を信じて法律の世界で彼なりに社会と戦う人物。ルディが声をあげても変わらない世間の目にはもどかしさを感じるばかりですが、ポールと価値観を擦り合わせ、どんな不利な状況でもマルコのために一枚岩となって世間に立ち向かう姿には心が救われます。


宮本演出の舞台版では、ショーパブのシーンをより多く盛り込み、エンターテインメント要素を強くしたそう。70'sのヒットチューンが飾る華やかなシーンはルディの力強い歌声に繋げ、静観な裁判シーンの冷たさを浮き彫りにしました。心を代弁する歌声を響かせたルディ役は東山紀之さん、ポール役は谷原章介さんが熱演し、大成功を収めた世界初演。公演を見逃した1人として、素晴らしい舞台の再演を強く願っています。 まるで現代日本を指摘するかのような問題提起。『チョコレートドーナツ』を見終えた時、あなたはどう感じますか。