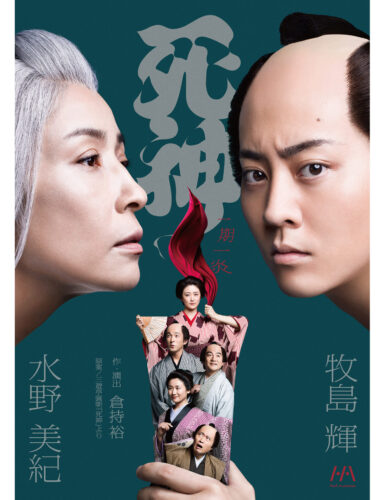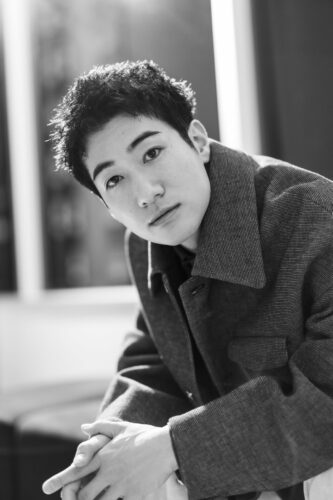映画化された作品も数多く、私たちにとって意外に身近な存在でもあるアメリカ演劇は、日本の演劇界にも大きな影響を与えてきました。現在でもPARCO STAGE(パルコ ステージ)やBunkamura、新国立劇場、文学座などで上演が行われています。
アメリカ演劇には数多くの劇作家が存在しますが、その中でも現代演劇の発展に大きく貢献した、5人の巨匠がいます。本記事では、ピュリッツァー賞受賞者を中心に、演劇史に名を刻んだ彼らの代表作と、それぞれの特徴について解説します。
アーサー・ミラー(1915-2005)
ジャーナリストの自由のために戦った劇作家
アーサー・ミラーは、後述のテネシー・ウィリアムズとともに、アメリカ演劇の芸術的水準を保った劇作家として知られています。
1915年、ニューヨークに生まれたミラーは、ミシガン大学在学中から戯曲を書きはじめ、『みんな我が子』(1945)、『セールスマンの死』(1949)や『るつぼ』(1953)など、多くの名作を生み出しました。
プライベートでは、女優のマリリン・モンロー(1925-1962)と結婚していたことも。また、執筆活動以外にも「国際ペンクラブ」の会長として、作家やジャーナリストの自由のために戦い続けた人物でもありました。
アーサー・ミラーの代表作は?
戦後アメリカ社会を描いた代表作『セールスマンの死』(1949)
ミラーの代表作として最も知られる『セールスマンの死』は、主人公ウィリー・ローマンを通して、戦後アメリカ社会の矛盾と人間の悲哀を描き、ピュリッツァー賞を受賞しました。
作中ではウィリーの回想がそのまま舞台の上で繰り広げられ、同じ空間に「現在」と「過去」という異なる時間軸が存在した、当時としては画期的な作品でした。
時間の飛躍は、俳優が瞬間的に演技を切り替えることによって表現されます。俳優にとっては、難しくも演じがいのある作品と言えるでしょう。
暴走する正義と暴力を描いた『るつぼ』(1953)
プロクターと一夜の関係を持った少女・アビゲイルは、彼の妻を陥れるために「魔女」として告発します。それをきっかけにして、村には「魔女狩り」の嵐が吹き荒れていき……。
本作の元になったのは、1692年にセイラムで起きた、アメリカ最大の魔女狩りです。
1692年2月から1693年5月までの16ヶ月間に約200人が魔女として告発され、19人が処刑されました。『るつぼ』が発表された当時のアメリカでは、マッカーシズム(共産主義の人物を告発する取り締まり運動)が横行しており、人々に大きな衝撃を与えました。
アーサー・ミラー作品の特徴は?時代や国を越える普遍性
アーサー・ミラーが育ったブルックリンには、当時、多くの移民が住んでいました。そのため彼は、多様な人種や価値観、歴史に触れて育つことになったのです。
ミラーはその中で、文化や社会体制、時代の違いがあっても、人々の抱える根源的な問題は普遍的なものだ、と考えるようになりました。
彼の作品が描き出す、人間の根源的な感情が、多くの人々に感動を与え続けています。
テネシー・ウィリアムズ(1911-1983)
名声と成功の裏で苦しみ続けた孤高の作家
テネシー・ウィリアムズは、アーサー・ミラーと同じく、1940年代に名声を確立させた劇作家です。ミシシッピ州コロンバスに生まれたウィリアムズは、不幸な家庭環境から、恵まれない青春時代を送りました。
1944年には自伝的演劇である『ガラスの動物園』がブロードウェイで上演され、大成功を収めました。その後、1947年に上演された『欲望という名の電車』、1955年の『やけたトタン屋根の猫』の2作品がピューリッツァー賞を受賞し、劇作家としての名声を手に入れます。
しかし、プライベートでは孤独に苛まれ、荒んだ私生活を送っていました。
テネシー・ウィリアムズの代表作品は?
ウィリアムズの自伝的名作『ガラスの動物園』(1944)
舞台は、不況時代のアメリカ合衆国・セントルイスの裏町。母アマンダと、ローラとトムの姉弟は、疲れた生活を送っています。
アマンダはローラに良い結婚相手にめぐり逢ってほしいと願うものの、ローラは極端に内気で、自身がコレクションするガラス細工の動物たちと過ごし、引きこもっています。一方、弟のトムは靴工場で働きながらも、詩人になるという夢を密かに抱いているのですが……。
ウィリアムズが自身と姉ローズをモデルにした、切なさに包まれた名作です。
南部貴族の没落と破滅を激しく描いた『欲望という名の電車』(1947)
南部の上流階級出身のブランチが、庶民的な義弟スタンリーと衝突する中で破滅していく悲劇です。現在でも世界中で上演され続けている人気作品で、日本でも多くの名優たちがブランチを演じています。
1952年には、ブロードウェイの舞台版で演出を務めたエリア・カザンがメガホンを取り、ヴィヴィアン・リー主演で映画化されました。
テネシー・ウィリアムズ作品の特徴は?繊細さの中にある歪んだ感情
ウィリアムズの作品は、「南部ゴシック」という文学ジャンルを確立しています。アメリカ南部の世間体の奥に潜む歪んだ精神性や、人種差別、貧困、犯罪などの社会問題にも切り込んでいるのです。どの作品でも、個人の内面に深く入り込み、時には人間の異常な在り方や狂気を描いています。
エドワード・オールビー(1928-2016)
「オフ・ブロードウェイの旗手」とまで言われた前衛劇作家
裕福な実家で生まれ育ったオールビーは、幼い頃から演劇に親しみ、劇作を続けていました。オフ・ブロードウェイで注目を浴び、「オフ・ブロードウェイの旗手」「アメリカ前衛劇の旗手」と評されました。
1958年『動物園物語』で劇作家としてデビューしたあと、初めてのオン・ブロードウェイでの作品『ヴァージニア・ウルフなんかこわくない』(1962年)が大ヒットしました。
『デリケート・バランス』(1967年)、『海の風景』(1975年)、『三人の背の高い女』(1994年)でピューリッツァー賞を3度受賞するなど、アメリカ演劇を語る上で欠かせない劇作家のひとりです。
オールビーの代表作は?
鋭い言葉の応酬が暴く、衝撃の真実『ヴァージニア・ウルフなんかこわくない』(1962)
46歳の大学教授であるジョージと、その妻バーサ。2人の家に、大学へ赴任してきたばかりの講師ニックと、その妻ハニーがやってきます。
やがて、2組の夫婦の間にある互いへの不満が次第に露見していくのですが……。
鋭い言葉の応酬が、スリリングな展開に発展していくという名作です。やがて発覚する衝撃の事実は、観客を驚愕させることでしょう。
ちなみに、タイトルの『ヴァージニア・ウルフなんかこわくない』は、ディズニー映画『三匹の子豚』(1933)の劇中歌『大きな悪い狼なんかこわくない』の替え歌です。
エドワード・オールビー作品の特徴は?登場人物の「言葉」を聞く独自のスタイル
彼の作劇法は、とても特徴的なものでした。通常の劇作で用いられる「プロット」(演劇作品の設計図)に縛られず、登場人物に自由に台詞を語らせる、というスタイルです。
自身の意識の中に登場人物が現れるのを待ち、彼らの言葉を吟味して一気に書き出すという方法が、鋭く痛々しい言葉の力を生み出したのかもしれません。
ソーントン・ワイルダー(1897-1975)
小説・劇作で両方に才能を発揮した、優れた作家
ソーントン・ワイルダーはアメリカの小説家であり、劇作家です。外交官の息子として、少年時代を中国で過ごしました。彼の小説家としての代表作は『サン・ルイス・レイ橋』で、こちらは1928年度にピューリッツァー賞を受賞しています。
ちなみに、演劇『わが町』(1938)も同賞を受賞していることから、ワイルダーは小説家としても劇作家としても大きな才能を持っていたことがわかります。
ソーントン・ワイルダーの代表作は?
何気ない日常を美しく描いた『わが町』(1938)
1938年に発表された『わが町』は、その年のピュリッツァー賞を受賞した作品です。アメリカの小さな町グローヴァーズ・コーナーズに暮らす、幼なじみのエミリーとジョージ。彼らを中心に、街の人々のさまざまな暮らしの様子が描かれた本作。
劇的なドラマは起こりません。特別な事件がないからこそ、日常のなかの何気ない瞬間の美しさと、生きていることの尊さが巧みに描かれた名作です。
ソーントン・ワイルダー作品の特徴は?いくつもの実験的要素
今日もなお世界中で上演され続けている『わが町』ですが、本作ではあえて舞台装置を設けず、ほとんど何もない舞台の上で、役者と観客の想像力によって舞台が進行するという技法が取られています。
現在ではこのような演出は珍しくありませんが、当時としては非常に画期的なものでした。
また、本作には舞台の進行役となる「舞台監督」という役が登場し、劇中で何度も観客に語りかけ、コミュニケーションをとります。
これは、演劇作品において「舞台上の世界」と「客席」を分断する「第四の壁」を壊すスタイルとして認識されています。
ワイルダーは自身の劇作において、これらの実験的な試みを繰り返していたのです。
ニール・サイモン(1927-2018)
現在も愛される、20世紀を代表するコメディ王
20世紀を代表するコメディ王として知られ、ブロードウェイに自身の名前を冠した劇場が建設されるなど、演劇界に大きな功績を残したニール・サイモン。ニューヨークのユダヤ人家庭に生まれた彼は、第二次世界大戦中からラジオ、テレビなどの喜劇脚本を多く手掛けました。
やがて創作の場をブロードウェイに移し、『おかしな二人』(1965)『裸足で散歩』(1963)などの劇作で人気作家となったサイモンは、長年にわたって精力的に新作を発表し続けました。
日本では、人気劇作家の三谷幸喜さんに大きな影響を与えた存在としても知られています。
三谷さんはサイモンの作品を観劇したことで演劇の道を志し、大学時代に旗揚げした劇団「東京サンシャインボーイズ」を、サイモンの『サンシャイン・ボーイズ』(1972)という作品から名付けました。
ニール・サイモンの代表作とは?
おじさんふたりのドタバタ同居劇『おかしな二人』(1965)
ポーカー仲間のたまり場となっているオスカーの部屋に、妻に逃げられたフィリックスが現れ、ふたりは奇妙な同居生活を始めることになります。
それまでは散らかり放題だった自分の部屋がきれいに掃除され、フィリックスの手の込んだ料理に満足するオスカー。しかし、次第に潔癖症なフィリックスとの対立が始まって…。
性格の正反対なルームメイト同士のドタバタを描き、現在も世界中で愛され続ける傑作コメディです。
ニール・サイモン作品の特徴は?笑いと涙で描く、人間の愛おしさ
サイモンの作品は、日常でのさまざまなシチュエーションから生まれる笑いを巧みに描いています。ハートフルな作風や台詞の言葉遊びが、日本でも高い人気を博しています。
ただ「面白い」だけの喜劇ではなく、人間の愚かさやおかしみを時にシニカルに、時に涙を誘う筆致で描いたサイモンの作品は、現在も多くの人々に愛されています。その人気と才能は「シェイクスピア以来の劇作家である」という意見が生まれるほどでした。
参考書籍:
『英米演劇入門』著:喜志 哲雄(研究社)
『世界文学大図鑑』著:ジェイムズ・キャントン ほか、日本語版監修:沼野 充義、訳:越前 敏弥(三省堂)
『洋書天国へようこそ 深読みモダンクラシック』著:宮脇 孝雄(アルク)