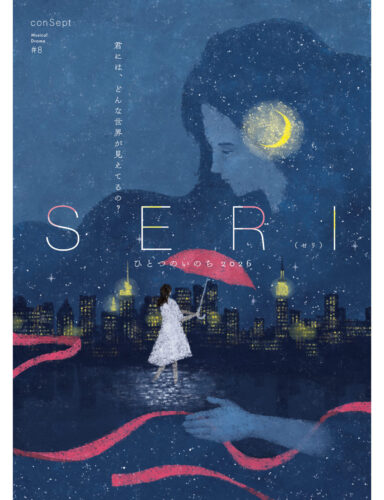2025年も、数多くの素晴らしい舞台作品が、わたしたちの心を揺さぶりました。幕が上がった瞬間、日常が消え去り、「喜怒哀楽のシャワー」が降り注ぐ。笑って、泣いて、考えさせられて……。そんな生のエンターテインメントが持つ熱量は、明日を生きる活力になったはずです。この記事では、今年上演された作品の中から、筆者が忘れられない3つの名シーンを振り返ります。
戦国時代に妻たちは天下泰平を願った。『まつとおね』

舞台は戦国時代。織田信長が亡くなった後、天下の覇権を争うことになる、前田利家と豊臣秀吉の妻たちを主人公に、戦乱を生き抜く女性たちの姿を描いた物語です。
戦国時代といえば、多くの大河ドラマや小説で武将たちの生き様が描かれてきましたが、本作はあえて妻たちの視点から描かれている点に強く惹かれました。その天下泰平への想いは、震災復興への希望と深く重なります。
上演の背景には、制作陣の強い覚悟がありました。プロデューサーは「このような状況下で舞台を上演してよいのか」と自問自答を繰り返したといいます。しかし、「舞台を通じて感動や笑顔を届けられたら」というエンターテインメントの本質に立ち返り、ふるさとの未来に向けて立ち上がったのです。
その想いは、確かに舞台上に息づいていました。被災した地元の人々、そして主演の吉岡里帆さん、蓮佛美沙子さんお2人をはじめとするキャスト・スタッフの祈りが込められた芝居は、観る者の心に小さくても確かな希望の灯をともしたはずです。いち演劇ファンとして、むしろこちらが救われてしまうような温かさに包まれました。
天下一を目指す夫たちに身を委ね、時代に翻弄されながら数多の苦しみを経験した妻たち。しかし、憎しみの連鎖を断ち切るために、「復讐」ではなく「赦し」が必要だと気づきます。あの時代も今の時代も変わらない真理であり、困難なときこそ「赦し」と「希望」を伝える役割が舞台にはあるのだと、改めて痛感させられた名作でした。
宇宙船内は「あいにく」だらけ!『リプリー、あいにくの宇宙ね』

近未来の宇宙船を舞台に、船長や乗組員、謎の漂流詩人などが入り乱れるSFアクション音楽コメディ。次々と襲いかかるトラブル、いわゆる「あいにく」な事態に巻き込まれながらも、歌と笑いで銀河を駆け抜けるドタバタ劇です。
わたしは男性ブランコの大ファンで、「どうしても見逃せない!」と、居ても立ってもいられず東京への遠征を決めました。 鑑賞後の脳内を占めたのは、「学園祭みたいなわちゃわちゃ感、てんこもりの情報量、しっちゃかめっちゃかな展開なのに、最後はすべてが美しく収束した」という驚きでした。
まさに感情のジェットコースターで、一度は振り落とされそうになったのに、幕が下りてしまうと、あの宇宙船内の大混乱が恋しくてたまりません。この世界観でしか味わえない「喜怒哀楽のシャワー」を全身で浴びたような高揚感がありました。
また、「音楽コメディ」という名前の通り、歌唱シーンも大きな見どころでした。特に主演の伊藤万理華さんは、乃木坂46出身ならではの伸びやかでキュートな歌声を披露。「一生懸命だけどちょっとうっかり、でも憎めない」という主人公のキャラクターが全開で、男性ブランコ目当てで観劇したはずが、気づけば彼女の虜になっていました。
物語には「感電するほどの絶望」も待ち受けています。けれど、信じた仲間たちとなら、それを面白がって乗り越えられる。それが例え宇宙のど真ん中でも。そんな真っ直ぐなメッセージに、最後は思わず涙がこぼれてしまう、笑って泣ける最高のエンターテインメントでした。
「役者人生における父」と作り上げた究極の二人芝居とは?『ライフ・イン・ザ・シアター』

劇場の楽屋と舞台裏を舞台に、若手俳優ジョンとベテラン俳優ロバート、2人の会話だけで紡がれる二人芝居。世代の異なる役者たちが、芝居論を戦わせ、日常を語り合いながら、月日と共に変化していく関係性と人生の哀歓を描き出します。
正直なところ、当初はこの作品を知りませんでした。しかし以前、シス・カンパニー公演『帰ってきたマイ・ブラザー』を観劇した際、「シス・カンパニーの作品は俳優も豪華でハズレがない」と感じたこと、そして堤真一さんと中村倫也さんの共演という点に惹かれました。
調べてみると、本作の日本初演は1997年。驚くべきことに、若手俳優のジョンを演じたのが堤真一さんでした。かつて新人役だった彼が、時を経て大御所ロバートを演じる。このキャリアの積み重ねが生む「結実」に、心が掴まれてしまったのです。
さらに胸を熱くさせるのが2人の関係性です。2009年の初共演以来、中村さんは堤さんを「役者人生における父」と呼び、最も慕う先輩として名前を挙げています。そんな実人生での師弟関係が、舞台上のロバートとジョンに重なり合う。こうした熱い人間関係に弱いわたしは、この舞台が気になってたまらなくなりました。
若い観客は、新人がベテランに憧れ、やがて追い越そうとする野心や疎ましさに共感するでしょう。一方、年配の観客は、かつての自分を若者に見出し、これから辿る老いの道に思いを馳せるはずです。人は誰もが変わっていくけれど、演劇という営みは変わらない。観劇後、「自分はどう老いていこうか」とふと考えを巡らせる、そんな演劇ならではの贅沢な時間を堪能させてくれました。

ジャンルは違えど、どの作品にも共通していたのは、心の機微を丁寧に掬い上げる演劇の底力でした。やっぱり舞台は、劇場という空間でしか味わえない特別な体験です。素晴らしい作品に出会うたび、もっとこの世界に浸っていたいと思います。2026年は、一体どんな作品が、どんな新しい景色がわたしたちを待っているのでしょうか?