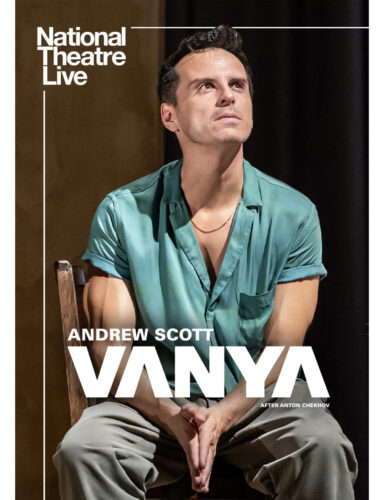2007年にピュリツァー賞を受賞した『ラビット・ホール』を、宮澤エマさん、成河さんら極上のキャストと、藤田俊太郎さんの演出で上演。その洗練された空間と、人間誰しもが経験する“喪失感”、リアルを追求した演出に圧倒されました。(2023年4月・PARCO劇場)※ネタバレ注意
4歳の息子を事故で亡くした夫婦に生まれる溝
本作は4歳の息子を交通事故で亡くしたベッカが、夫のハウイー、妹のイジー、母のナット、そして交通事故を起こした高校生ジェイソンとの交流を通して再生していく物語です。2007年にピュリツァー賞を受賞、2010年にはニコール・キッドマンの製作・主演により映画化されました。
『ラビット・ホール』で特徴的なのは、事故の直後の爆発的な悲しみや動揺ではなく、事故から8ヶ月経った家族を描いていること。日常的で時に笑える会話を重ねながら、少しずつ妹や母親の言動にイラついたり、夫との溝を感じたりするベッカ。
妹も母親もベッカとハウイーを気遣っているし、ベッカとハウイーは互いに話し合い、歩み寄ろうとしています。しかし毎日毎秒、息子の面影を感じすぎるからこそ遠ざけようとするベッカと、息子のビデオを見続けることで息子の面影を感じようとするハウイーは支え合うことができません。悲しみ方も、傷の癒やし方も人それぞれであり、どちらかが正しいわけでも、どちらかが間違っているわけではない。それは誰もが経験したことのある、人とのすれ違いにも当てはまるように思います。
交通事故を起こした車を運転していた高校生ジェイソンは、一見ズカズカと被害者の家族に踏み込んでいく空気の読めなさを感じますが、物語が進んでいくうちに、彼もまた彼なりの方法で、前に進む道を探っているのだと感じます。
本作の舞台は2003年以降のアメリカですが、“喪失と再生”のテーマは多くの人々の人生に重ね合わせられます。筆者が今回感じたのは、コロナ禍で感じた喪失感。2020年初め頃は、もうこの世の中に希望はないのではないかと感じるほどの思いでしたが、今は悲しみや喪失感を持ちながらも、前に進んでいる気持ちがします。本作にある、“耐えられない重みが少しずつポケットの中にあるレンガくらいになって、思い出さない時間もある。でも消えることはないし、消えなくていい”というメッセージが体に染み込んでくるような感覚でした。
リアルを追求したキャストと演出
ベッカを演じる宮澤エマさんと、ハウイーを演じる成河さんは、どちらも愛情や気遣いを持っているのに寄り添えない、もどかしい夫婦を上質に演じ抜きます。繊細な心の揺れ動きを感じさせ、時に強弱も見せる極上の会話劇です。
そこに時に余計な一言も挟みながら、家族の日常と、根底にある愛情を感じさせる妹イジーを演じる土井ケイトさん、母ナットを演じるシルビア・グラブさん。この家族のバランスが絶妙で、本作は喪失だけではない、再生の物語であることを感じさせてくれます。そして、本作のキーポイントとなる高校生を演じる阿部顕嵐さんも異質なキャラクターを好演(山﨑光さんとのWキャスト)。
人間は誰かの思い通りにはならないし、安直に同じ方向を向くことはできない。時に常識も通じない。でもバラバラな5人が混ざり合い交流していく中で、なぜか少しずつ希望が生まれていく。そんなリアルな関係性が印象的でした。
また本作を魅力的にしているのが、“リアルな演出”です。演劇では何かを飲む・食べるといった行為を実際に行うことはなく、フリで観客に想像させることが一般的ですが、本作では登場人物たちが本当にミルクを飲み、お菓子を食べ、テレビに流れるビデオを見ます。それがより目の前に息づく“人間のリアルさ”を演出しているように感じられました。
大きなセット転換のない会話劇ながらも、天井や照明の動きで各シーンが移り変わり、役者の卓越した演技力で心を掴み続ける。心に様々な示唆を投げかけてくれる圧巻の舞台でした。
『ラビット・ホール』は4月25日までPARCO劇場で上演中です。


観劇後、しばらく1人でゆっくりと、いつもは見ないふりをしている喪失感と向き合うことができた気がします。