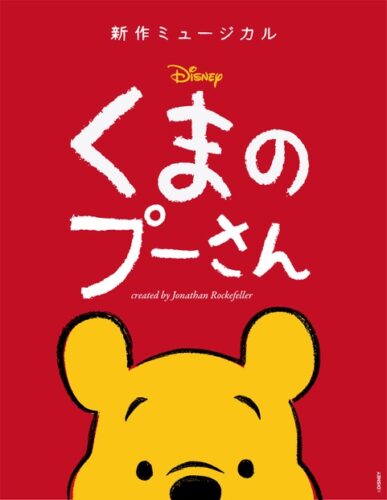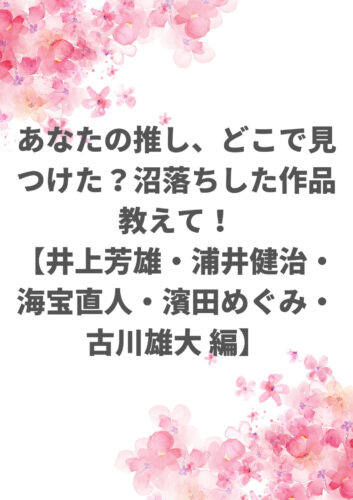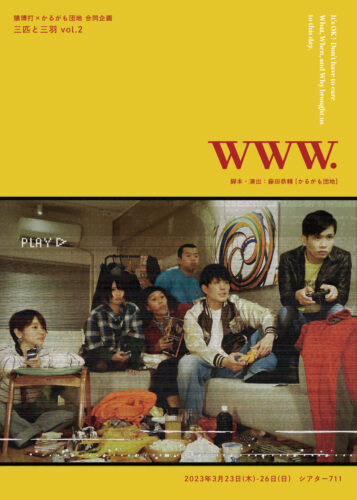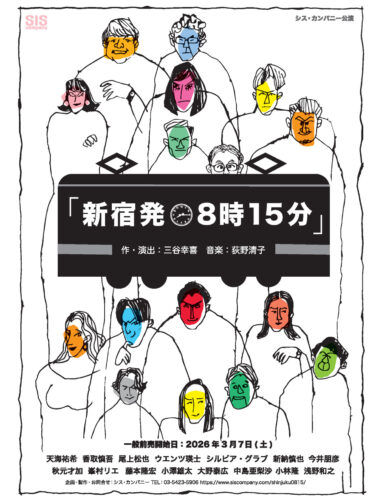舞台手話通訳は、聴覚に障がいのある方の観劇をサポートする手段のひとつ。最近ではミュージカル『SIX』や『アニー』で舞台手話通訳付き公演が実施され、話題を呼びました。そこで今回は、舞台手話通訳とは一体どんなことをするのか、詳しく紹介します。
舞台手話通訳とは?
演劇やミュージカル、音楽ライブといった舞台で、ステージから発信される音情報を手話で伝える仕事が「舞台手話通訳」です。舞台の上手や下手に立って手話通訳するか、ステージの中に入って時には役者と同じように演技しながら通訳するか、大きく2つのタイプに分けられます。
一般的な手話通訳では、通訳者がリアルタイムで流れる音声や会話を同時進行で手話に変換します。これにより、聴覚に障害のある方が状況を把握し、周囲と円滑にコミュニケーションを取れるようになります。
一方で、舞台手話通訳の場合、まずは台本の内容を手話に翻訳するところから始まるのが大きな特徴です。本来は文字から音になる情報をどうやって手話に置き換えるのか、演出家やろうの監修者と相談しながら決めていきます。そのなかで舞台通訳者自身が台詞に込められた意図やダジャレ、韻を踏んだ歌詞など細かなニュアンスまで丁寧に拾い上げ、表現に落とし込んでいく過程が重要となります。
そして、舞台手話通訳者がキャストとの稽古に参加し、事前に翻訳した手話をブラッシュアップしていく段階へ。時には演出家から、「役者と同じ表情や動きをしてほしい」「登場人物の背景にある感情を表してほしい」などとリクエストされることもあるのだとか。
さらに、舞台通訳はステージで流れる音楽や効果音などを知らせる役割も担っています。とはいえ、役者の台詞も含めれば、すべての音情報を1人で表現するのは不可能。そのため、「ここで一番伝えたいのは何か」を考えながらベストな表現を探っていく姿勢が求められます。
このように舞台手話通訳者は一時的なサポートに留まらず、カンパニーの一員として作品と真摯に向き合っているんです。
観劇の楽しさを届けるために
イギリスやアメリカなど海外の演劇界を見てみると、舞台手話通訳が観劇サポートの選択肢として普及しています。例えば『ライオンキング』のようなロングラン作品では、定期的に舞台手話通訳付き公演が行われています。
しかし、日本では舞台手話通訳の認知度が低いうえに、上演予算の関係もあってなかなか実施できていないのが現状です。
ただ、最近は小劇場や一部の劇場を中心に、舞台手話通訳を取り入れる動きが徐々に広がってきています。
2025年2月にはミュージカル『SIX』の日本キャスト版にて、東京公演のうち2回を舞台手話通訳付きで上演。対象公演では、舞台手話通訳者に近い前方サイドブロックの座席が鑑賞サポート席として用意されました。また、直近の5月7日まで上演していたミュージカル『アニー』の東京公演でも、舞台手話通訳付き公演を2回実施。こちらも見やすさに配慮して舞台手話通訳対象席が設けられました。
さらに、ロングラン上演中の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』でも、2025年5月17日に舞台手話通訳付き公演が実施され、5月24日に2回目の公演が行われる予定です。
少しずつ舞台手話通訳を体験できる機会が増えてきている今だからこそ、定着させるためには主催者と観客の双方で理解を深めていくことが大切ではないでしょうか。障がいの有無にかかわらず誰でも観劇を楽しめるサポート方法について、皆で考えていきたいですね。
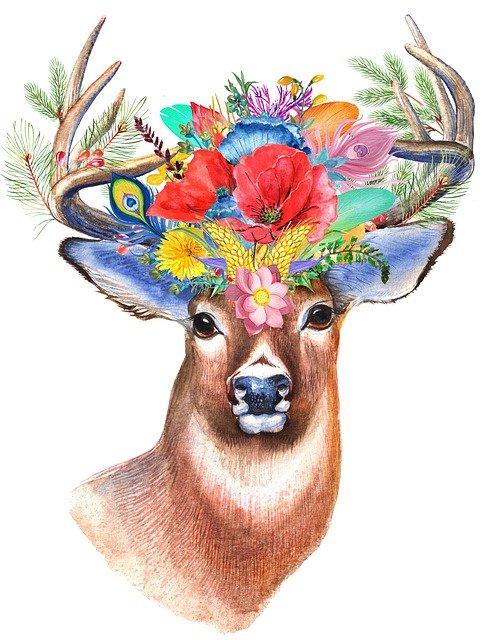
舞台手話通訳では台本を手話に翻訳し、稽古を重ねていくというところに「より良い表現を届けたい」という熱意を感じました。筆者も観たい作品に舞台手話通訳付きの公演があるかどうか、注目したいと思います。