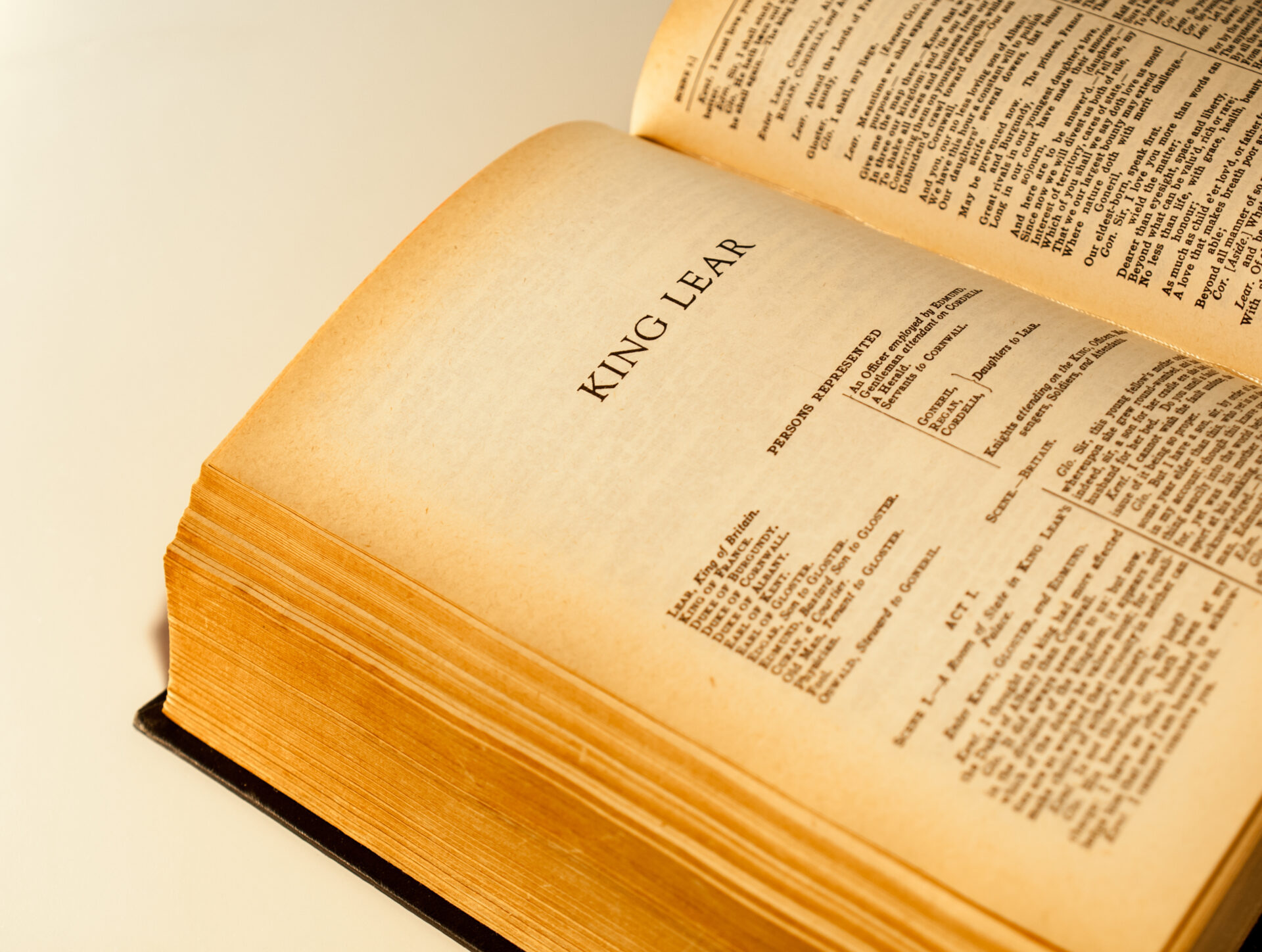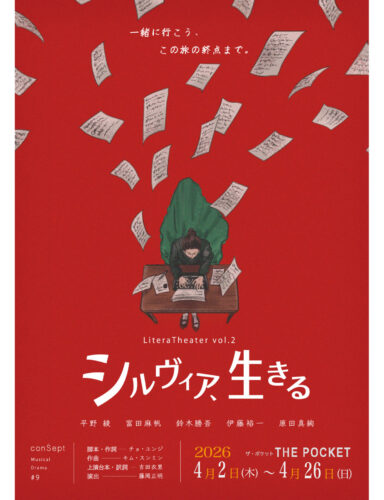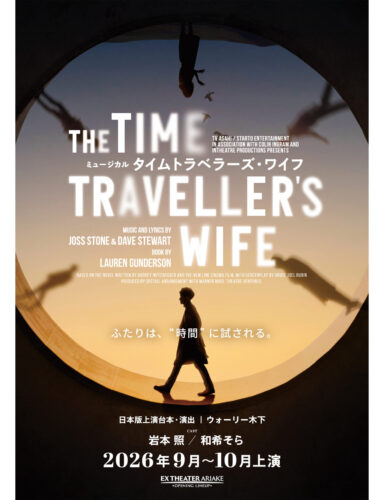『リア王』は、イギリスの劇作家ウィリアム・シェイクスピア(1564-1616)の「四大悲劇」の中で、「最も悲劇的」と言われる傑作です。親子愛と裏切り、権力への欲望、そして人間の本質を鋭く描いた本作は、400年以上経った今でも私たちの心に深く刺さる物語です。この記事では、そんな『リア王』のあらすじと名台詞をご紹介します。
『リア王』のあらすじ
古代ブリテンの王・リアは、年老いたことをきっかけに、3人の娘たちに領土を分配し、隠居生活に入ろうと考えています。リアは娘たちに「誰が最も自分を愛しているか」と尋ね、娘たちの愛を試すことにしました。
長女のゴネリルと次女のリーガンは大げさな言葉でリアをほめちぎり、それぞれに広大な領土を手にします。しかし、リアに最も可愛がられていた末娘のコーディリアは、口を開こうとしません。
コーディリアは姉たちに対し「なぜお姉様たちは夫がありながら、お父様だけを愛するなどと言うのでしょう」と投げかけます。そして「私は、お姉さまたちのようには結婚しません」と誠実な思いを訴えるのですが、リアには彼女の真意が理解できません。リアの怒りを買ったコーディリアは、国を追放されてしまいました。
ゴネリルとリーガンの屋敷に身を寄せることになったリア。そこで待っていたのは、手のひらを返したように冷淡な娘たちでした。失意のリアは、やがて狂気に蝕まれていきます。
3人の娘たちの真意に気付けなかったため、次々と巻き起こる悲劇。リアの忠臣であるケントやグロスター、グロスターの嫡子と私生児であるエドガーとエドマンドなど、さまざまな登場人物の人間ドラマも交錯する名作です。
人生の真理を突く『リア王』の名台詞
『リア王』には、人生の真理を突く名言がたくさん登場します。その中でも、現代の私たちの心に深く刺さる5つの名台詞を紹介します。
「私は子として陛下を愛しております。それ以上でも以下でもありません」(コーディリアの台詞、第1幕第1場)
第1幕第1場で、父への愛を試されたコーディリアの台詞です。
「それ以上でも以下でもありません」という言葉は、一見そっけなく感じるかもしれません。しかしコーディリアは、「父から与えてもらった愛に見合う愛を返す」と考えています。
リアは娘たちから大げさに褒められることを望んでいますが、真実の愛は華美な言葉ではなく、誠実な行動に現れるものです。コーディリアの深い思いが込められた名台詞です。
「何もないところから何も出てきはせぬぞ」(リアの台詞、第1幕第1場)
同じく第1幕第1場、コーディリアから「言うことは何もございません」と言われた時のリアの台詞です。
リアは娘たちからの言葉のプレゼントを求めていますが、コーディリアはそれに応じようとしません。自分への愛を催促する台詞に聞こえますが、「何もないところから何も出てきはせぬぞ」という言葉は、リアの娘たちへの愛そのものを示している、とも考察できます。
娘たちに無条件の愛を注ぐのではなく、甘い言葉を語らせ、それに応じて領土を与えるというリアの考え方こそが、愛を失うきっかけになったのかもしれません。
「リアの影法師だい」(道化の台詞、第1幕第4場)
長女ゴネリルの館に身を寄せたリアは、ゴネリルや彼女の召使いからひどい扱いを受けてしまいます。自分がこんな扱いを受けるのはふさわしくない、と嘆くリアに、お付きである道化が言った台詞です。
リアが王であった頃は、人々はその権力や肩書きを敬っていたのでしょう。
ですが、王の立場を失い「ただのリア」となった今、リアはかつての自分の「影のような存在」に過ぎないのです。
この台詞には、『人間が他者を肩書や社会的な地位で判断すること』への皮肉が効いています。
「人は生まれると、この阿呆の大いなる舞台に出たと知って泣くのだ」(リアの台詞、第4幕第5場)
ゴネリルとリーガンに裏切られ、嵐の荒野をさまよった後、狂気の中でリアが発する台詞です。
赤ん坊が泣く、という自然現象を「この世界の本質を理解して嘆く」と捉えている、リアの悟りが感じられます。「阿呆の大いなる舞台」というのは人間社会全体を表した言葉で、非常に哲学的な表現です。
物語を通して、リアは数えきれないほどの悲しみや絶望、権力を持つことへの虚しさ、後悔などを味わってきました。それらの経験が、この台詞に集約されているのではないでしょうか。
「運命の糸はちょうどひとまわりして、俺はこのざまだ」(エドマンドの台詞、第5幕第3場)
エドマンドはリアの臣下・グロスターの息子です。兄のエドガーとは違い、愛人との間に生まれたために「私生児」として扱われているエドマンドは、父を騙してエドガーを追放してしまいました。
権力を狙うエドマンドは、ゴネリルとリーガンの両方に偽りの愛を囁き、リーガンの夫の座を手に入れようとしますが、帰還したエドガーによって粛清されてしまったのでした。
この台詞は、エドマンドの最期の台詞として語られています。悪事は必ず自分に返ってくるという「因果応報」の考え方が読み取れます。
河合祥一郎さんによる『新訳 リア王の悲劇』(角川文庫)では、エドマンドのこの台詞について「エドマンドはどん底から運をつかんで運命の糸車の最も高いところまで上がりながら、糸車は一周して、またどん底へ落ちてしまったということ」と解説されています。
参考書籍:シェイクスピア・著、河合祥一郎・訳『新訳 リア王の悲劇』(角川文庫)

今まで、『リア王』とは「老いが招く悲劇」を描いているのだと思っていました。しかし、改めて本作の名言たちに触れてみると、この物語には「因果応報」の皮肉が込められているのではないかと感じています。