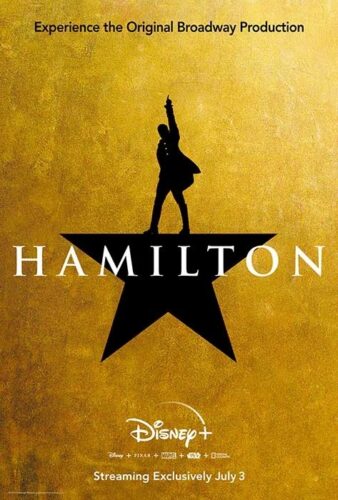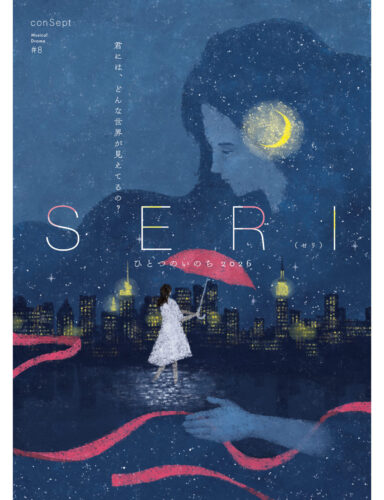『時をかける少女』(2006)、『サマーウォーズ』(2009)、『竜とそばかすの姫』(2021)等を世に送り出してきた、スタジオ地図。2015年に公開した『バケモノの子』が劇団四季にて4月30日(土)からミュージカル作品として上演されています。本記事では、熊徹と九太(蓮)の関係性から、現代の家族像やアイデンティティについて考察していきます。作品についてはこちらから。
血の繋がりを超えて結ばれる“家族”としての絆
主人公の蓮は、父母が離婚した後、9歳の時に一緒に暮らす母が事故で亡くなります。親戚に引き取られることを拒否したため、身寄りが無くなった蓮。警察の補導から逃れるために、渋谷の街を走り回り、入り込んだ路地からバケモノの世界“渋天街(じゅうてんがい)”へと迷い込みます。
そこで、粗暴で弟子がいないために宗師になれない熊徹(くまてつ)と出会い、人間界へ戻っても居場所のない蓮は、強さを求めて弟子になります。熊徹によって、九太と名付けられ、不思議な共同生活が始まります。
その後、成長した九太が偶然人間界へと戻った時、自分の血縁の父親と再会を果たします。会わなかった間、どのように息子が過ごしていたか知らないのにもかかわらず、無意識に「寂しかっただろう」と九太の気持ちを決めつけてしまう父。そんな父に対して、“寂しいと決めつけるな”という九太の反論、そして、熊徹と九太の、血縁関係なしに強い絆で結ばれた姿を描くことで、ステレオタイプな“両親ともに揃っていることが幸せ”という「家族」への考え方に警鐘を鳴らします。
「僕は父親とお酒を一緒に飲んだり、語り合ったりする前に亡くなってしまった。父親の存在がその距離感で止まっている。それが作品に出ているのかもしれない。」と以前インタビューで語っていた細田守監督。現在の多種多様な家族の在り方を肯定してくれる。また家族の在り方について観客に考えさせる作品になっています。
一郎彦にみるアイデンティティとの戦い。「自分は何者であるか」という問い。
バケモノたちの世界では、“人間は心に闇を抱えおり、闇に漬け込まれて手に負えなくなってしまうと大変な事態が起こる”という理由から人間を弟子に取るのは御法度とされています。熊徹のライバルの猪王山(いおうぜん)は、渋谷の路地に捨てられていた一郎彦を見つけ、“自分が育てれば心の闇など生まれない”という慢心から、「人間の子」ということを隠して育てることにしました。
しかし、一郎彦は、成長するにつれ、父親と自分の容姿が異なることに疑問を持ち、「自分は何者なのか」という問いに悩まされることとなります。この悩みこそ、心に抱える闇なのです。一郎彦は、自分は父親とは違うかもしれないという疑念を持ちながらも、“父親に認めてほしい”という想いで、心の中の闇に飲み込まれてしまいます。
一郎彦は人間であることを隠されて育てられたために、バケモノの世界にも、人間界にも居場所がなく、アイデンティティが喪失されてしまったのです。
現代では、変動していく社会を生きていくために、相手との関係性や、所属場所での自身の役割によって、様々なアイデンティティの使い分けが求められています。しかし、このために現代は、「アイデンティティ」の喪失を招きやすい世の中となっています。現代を生きる私たちは常に「自分は何者であるか」という問題を抱えています。そんな私たちの姿を鏡のように写し、戦うキャラクターが一郎彦だと考えられます。

ファミリー向けの作品に見えて、大人にも刺さるテーマで作品が描かれているので、老若男女、世代・性別を超えて引き込まれる作品になるのではないでしょうか?