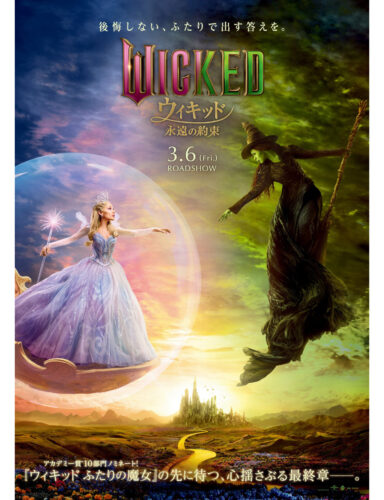文学界の異端児オスカー・ワイルドと、友人ロバート・ロス、小説「ドリアン・グレイの肖像」の主人公にそっくりな青年アルフレッド・ダグラス、3人の男の物語を描いた韓国発のミュージカル『ワイルド・グレイ』。福士誠治さん、立石俊樹さん、東島京さんが演じたゲネプロの様子をお届けします。
「自分の生き様に美しさを求めていく舞台」
脚本イ・ジヒョン、作曲イ・ボムジェによって、2021年に韓国で初演を迎えたミュージカル『ワイルド・グレイ』。日本版では本作がミュージカル初演出となる根本宗子さんが演出・上演台本・訳詞を担当し、福士誠治さん、立石俊樹さん、東島京さん/平間壮一さん、廣瀬友祐さん、福山康平さんのチーム固定でのダブルキャストで上演されます。

19世紀末、ロンドン。オスカー・ワイルドが連載した「ドリアン・グレイの肖像」は時代に合わない破格的なテーマと内容で英国社会に衝撃を与え、主人公のドリアンが死を迎えるという望まない結末で小説が出版されました。そんなワイルドを支え続けるのは、友人であり支持者であるロバート・ロス。
芸術の中でさえ自由は叶わないのか。そんな最中、ドリアン・グレイは自分にそっくりだと話す青年アルフレッド・ダグラス(通称ボジー)が現れます。美しく、ワイルドの小説に心酔し、危うげな雰囲気を纏うボジーに惹かれていくワイルド。

ロスはボジーの危うさを忠告しますが、ワイルドは既に聞く耳を持ちません。ボジーは父から受ける暴力に悩み、どんどんと精神的に不安定になっていき、ワイルドに様々な要求を突きつけるようになります。

オスカー・ワイルドを演じる立石俊樹さんは、登場早々に客席にお茶目に語りかけ、ナルシシズム感のある振る舞いに笑みが溢れます。対してロス役の福士誠治さんは「すみませんね」とフォローしながらツッコミを入れるなど、どんな作品だろうかと身構える身体の力をふっと抜いてくれる冒頭です。ワイルドとロス、2人の和やかな掛け合いから、2人の確固たる信頼関係が伺えます。
またピアノ、チェロ、バイオリンの旋律が印象的な本作では、バイオリニストがワイルドのすぐそばで演奏するなど、音楽も作品の一体となっていることが感じられます。

一方、ワイルドの運命を変えるダグラス(ボジー)を演じる東島京さんは、セクシーさもある華やかな佇まいと、深い孤独、知性を絶妙なバランスで魅せ、ワイルドを自分の世界へと惹き込んでいきます。ワイルドは「小説の世界に入り込んでしまったかのよう」と語りますが、「迷い込んでしまった」と言った方が近いのかもしれません。

ワイルドを妖しく誘惑し、自分だけを見てほしいと責め立てるボジー。自己中心的に見える振る舞いも多いですが、愛に飢え、愛を渇望する姿に、ワイルドは他にはない強い引力を感じてしまったのでしょう。立石俊樹さんはワイルドの行く末をスマートに、しかし繊細に描き出します。

天才で異端児なワイルドをそばで支え続けるロスは、誰もが共感しやすいキャラクターかもしれません。福士誠治さんはボジーとの世界に没入してしまうワイルドを見つめる苦しい役どころながら、温かく深い愛情を持ったロス像を作り上げています。
イギリスの深い霧が客席にまで充満し、客席通路をワイルドとボジーが歩くとまるで2人の密会を覗き見しているよう。作品の世界にどんどんとのめり込む演出は、新国立劇場 小劇場の劇場サイズにもマッチしているように感じました。
福士さんは開幕にあたり、「偉大な小説家であるオスカー・ワイルドに惹かれるロバート・ロスという役を演じることは、楽しくもあり、切ない気持ちにもなります。今とは違う時代を生きた人達が、時代や社会にそして人間に翻弄され、苦しみながらも自分の生き様に美しさを求めていくこの舞台を、是非楽しんでいただけると幸いです」とコメント。

立石さんは「芸術、愛を求め続けた3人の男たちの物語です。オスカー・ワイルドという人物の魅力を知り、劇を通して彼自身の想像もし得なかった苦労や喜びを追体験させていただいています。ピアノ・バイオリン・チェロのみで紡がれる音楽は、とても美しく素敵な空間を演出してくれます。そして、役者3人だけのミュージカルだからこそ生まれる、濃密で深みのあるお芝居と心を震わせるミュージカルナンバーをぜひ劇場で堪能していただけたら嬉しいです」とコメント。
東島京さんは「多くの方はアルフレッド・ダグラスに感情移入できないかもしれませんが、図々しいくらい彼を愛してきたので彼なりの言い分を代わりに届けられるよう全身全霊でつとめてまいります」と意気込みました。

ミュージカル『ワイルド・グレイ』は、1月8日(水)から1月26日(日)まで新国立劇場 小劇場にて上演。2月には名古屋・大阪・高崎公演が行われます。公式HPはこちら

女性の恋心を鮮やかにリアルに描き出す根本宗子さんがなぜ、男性3人の物語を初のミュージカル作品に選んだのか疑問に思っていたのですが、観劇してみると本作にも根本さんが求める「愛」があったのかなと感じました。