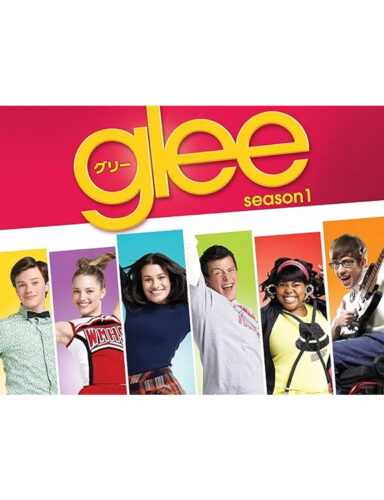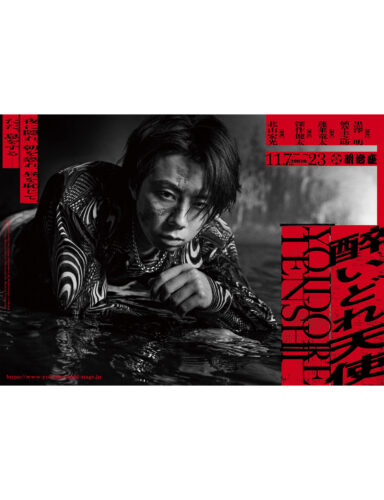2011年に『スリープ・ノー・モア(Sleep No More)』が世界を魅了して以降、日本でも着実に注目を集めているイマーシブシアター。観客が客席に座って舞台上の作品を鑑賞するのではなく、ホテルなど空間全体でパフォーマンスが展開され、その中を観客が動き回るなど、作品の世界に没入できる新しい観劇体験です。そして2023年、東宝演劇部が初めてイマーシブシアターの制作協力を行うことに。それがdaisydoze(デイジードーズ)の新作公演『Anima』。作・演出の竹島唯さんと、アートディレクション・演出の近藤香さんにお話を伺いました。
無意識のうちに作品の一部になれる。その裏側に隠された緻密な計算
−「没入型演劇」「体験型演劇」などと呼ばれるイマーシブシアターですが、お二人はイマーシブシアターとはどのようなものだと定義されていますか?
近藤「私たちは、作品の一部になるということをお伝えさせていただいております。作品の一部になった先に没入していくといいますか、いかに私達の作っている世界の一部として溶け込んでもらえるかというところを意識して作っていて、それを今イマーシブシアターと呼んでいると思います」

−作品の一部になってもらうために、こだわられている点は?
竹島「イマーシブシアターには観客が空間内を自由に動き回って体験する自由回遊型と、キャストの誘導によって移動しながら体験する誘導型があって、私たちは誘導型でやっています。小さな部屋に本当に少人数、例えば2人しかこの世界にいないんじゃないかという気持ちになれることによって、没入していけると思うので、そういった体験を緻密に計算しています」
近藤「誘導型の魅力は、無意識のうちに段々と世界にのめり込んでいけるということです。自由型だと自分が動いているという現実的な意識を持たせてしまうので、そういった意識を持たせないようにこだわっています。例えばホテルのマネージャー役の役者が観客を次の部屋にお連れする、その時にどういう意味を持たせて次の部屋に誘導するのか。そういった点を演者が意識することで、観客は自然に導かれるままに作品に没入していけるのではないかと思いますね」
−確かに、自由回遊型の場合、自由にと言われてもどう動いて良いか分からず、他の観客の動きを真似するなど、なかなか世界に没入することが難しいことがありました。
竹島「そこは凄く意識していて、例えば1人のキャストの周りに人がたくさん集まると、人垣の中でパフォーマンスを見なければいけなくなって、それが果たして没入なのかというのは難しいですよね。もちろん世界には没入しているのですが、見ている時に観客の中に友達を見つけたりしたら、一瞬意識が現実に戻ってしまう。なるべくお客さんが廊下や階段ですれ違わないように動線もかなり工夫していて、体験としても没入させられるかというのは、私たちが意識している部分です」
−となると、かなり構成が難しそうですね。
竹島「そうですね。同じホテル内で様々なキャラクターのシーンが同時進行で一斉に進んでいくので、15秒ごとに誰がどう移動するかを綿密に計算しています。誘導型なのでお客さんがどういうフローを踏んでいくのかというのはなんとなく見えているのですが、分岐点がいくつもあるので、どう分岐していくかは偶然の産物です」
−15秒ごとに?!制作期間はどのくらいなのでしょうか。
竹島「本作は1年かけて創っています。3〜4ヶ月で制作したこともあるのですが、かなり大変でした」
−演者の皆さんも理解して、覚えて、演じるというのは非常に難しそうですね。
竹島「はい。何分何秒にこのドアを開けなきゃいけない、とか決まり事も多いですし、全てのタイミングが合わないとズレていってしまいます」
近藤「まず決まり事を頭に叩き込んでください、というのは口酸っぱく言っているよね。覚えたら余白が生まれて、作品性を考えていくことが出来るので」
竹島「そういった点では、今回は普段ミュージカルに出演している俳優さんたちが出演してくれるというのは大きいです。ミュージカルに出演している方々は、自分の役としてやるべき動きと、作品を俯瞰で見るということを日常的にやっている方々なので。覚えることが多くても、作品の中の自分の立ち位置がどこなのかを考えながら芝居をしてくれるので、それに他のキャストも影響されていて、良いコラボレーションになっているのではないでしょうか」

−東宝演劇部の制作協力という観点で、今までとは異なる新しい要素はありますか?
竹島「役者が入ること、歌が入るということは新しいです。出演者の中村翼くんと話していて気づいたのですが、本作では1シーンごとに入口と出口を決めていて、それがミュージカルと非常に近しいんです。例えば入口では主人公のユングと妻が幸せな状態だけれども、段々と心が離れていく踊りや歌を経て、出口では妻が悲しんで出ていく。ミュージカルも1曲の歌の中で心が変化していく様が描かれますよね。そこは凄く共通していて、歌や演技が入ることで、今までのダンスだけでは成立しきれなかった部分まで描けるようになったかなと。そういった意味では、ミュージカルを再構築しているような作品になるんじゃないでしょうか」
上演場所の歴史や神話から生まれる、daisydoze作品が纏う空気
−daisydoze(デイジードーズ)の作品の特徴として、実在する場所の歴史や神話を活用するというのがあるように思いますが、いかがでしょうか?
竹島「私達が一番大切にしているのは場所なんです。まず上演する場所を見に行って、その場所にどんな物語を感じるかを重視しています。今回の『Anima』も日本橋の歴史や神話はかなり調べていますし、日本橋でバーやレストランを開いている方達にもお話を聞きました。また上演するBnA_WALLはアートホテルで、全客室がアート作品になっているので、実際に私たちも泊まらせて頂いています。アートの部屋に“泊まる”というのは単にアートを見るのと全然違う体験で、アーティストの思考や想像の中に自分がいるような感覚なんです。そういった場所で感じるものを作品に落とし込んでいくのがdaisydozeの特徴になっていますね」
近藤「本作は今までの私たちの作風と比べるとモダンな印象があると思います。それは日本橋が醸し出す空気の中で感じたことで、同世代の方がお店を開いていることも多く、革新やニューウェーブな空気が強かったからなんです。反対に、前作の浅草を舞台にした作品では芸者さんたちの伝統を守る・継承することに価値を置いている場所でした。場所の空気感やその土地の方々にヒアリングしていく中で、生まれるダンスや衣装は全く変わっていきますし、作品の色付け方が変わっていくんだなというのはやりながら感じています」

−キャストに対してもそういったインプットをされるのでしょうか?
竹島「そうですね。本作で言えば、ホテルにだいぶ泊まり込みをさせて頂いて、みんなで日本橋の街を歩いたり、日本橋で暮らす方々にお話を聞く機会もありました。体験として取り込んでもらった上で表現に落とし込めるような場はすごくあります」
近藤「キャストの皆さんの出演動機は色々とあると思いますが、私たちは表現の手前の情報の個性が強いので、そういった部分に面白さや新しさを見出して出演を決めてくれる部分も多いのかなと思います」
ユングを軸に描かれる喪失と再生の物語
−色々なインプットを経て、『Anima』での作品のテーマとしていることはありますか?
竹島「『Anima』では主人公のユングが、妻を失った悲しみから、自分を見つけて立ち直るっていうプロセスを描いています。ユングの心理学の研究によれば、人は悲しみから立ち上がるプロセスがあるんです。まずは悲しんだり傷ついたり、喪失感を得る。その中で自分が悲しんでいることに気づくことで、人は立ち上がって再生していきます。どんなに悲しいことがあっても、自分をちゃんと持って、自分を受け入れて立ち上がれるのが人間なのだというのはテーマとして大事にしているし、コロナ禍や戦争もある世の中で、社会と繋がるテーマなのかなと思います」
近藤「唯さんとは一緒に過ごす時間が長いので、その中で“こういう気持ちが大切だよね”と等身大に感じている気持ちからテーマが抽出されているように思います。社会に対してこういうメッセージを伝えたい、という視点からテーマを決めるのは少し烏滸がましいというか。日常生活の中で感じることをコアに、そこから世界を広げているという感覚です」

−本作でユングをテーマにした理由は?
竹島「本作の元になっているのは、昨年上演した『Dancing in the Nightmare −ユメとウツツのハザマ−』という作品で、“日本橋 竜宮城の港なり”という言葉から浦島を主人公に描きました。制作過程の中でキャラクター性を強めたいと考えていた時、ユングの元型論というのを知って。例えば日本の神話と同じような内容がギリシャ神話の中にもあって、人間の根底にある共通の心のパターンがあるという論で、その中にトリックスターやシャドーなどの元型があるのですが、それらが浦島のキャラクターにピッタリとハマっていることに気づいたんです。それで、昨年も元型論を元にキャラクター像を深めていったのですが、今回はよりユングやユングの周辺人物に重きを置いて作品を創っていくことにしました」
−なるほど。ということは、作品のキャラクターもユングの心理学という現実とシームレスに繋がっているのですね。
竹島「そうですね。誰もが夢を見るという体験はしたことがあると思いますので、その夢の中に入るという体験は面白いんじゃないかなと思います。ユングについても調べていただくと、作品での気づきがあると思いますね」
『スリープ・ノー・モア』を観て感じた現実世界との距離の近さ
−そもそも、お二人がイマーシブシアターに出会ったきっかけは?
竹島「私は2016年に『スリープ・ノー・モア』を観劇しました。今までミュージカルや演劇作品はたくさん見てきましたが、これまでに観たことがないものだったので、混乱したんです。“凄く疲れたし、何を観たのか分からない”とちょっと怒っていたくらい。そのぐらいの衝撃があったと共に、私も作れると思ったんです。日本発のミュージカルを自分は作れないなと思っていたけれど、もしかしたらイマーシブシアターは日本発のものを世界に持っていけるんじゃないかなと思えて」
−なぜ“作れる”と感じられたのでしょうか?
竹島「ミュージカルに抵抗がある人は“なんで突然歌い出すんだろう”とよくおっしゃると思うのですが、それは現実の中で非現実を見ているからギャップを感じるんだと思うんです。でもイマーシブシアターは自分の世界線の中に作品が来る感覚があって、物理的な距離も心理的な距離も近いからこそ、違和感がなくなる気がしたんです。だから日本でも舞台作品という世界線に入りやすいんじゃないかと思いました。
それに、日本を舞台にした作品を創ることで、海外の観光客が感じている日本の神秘的な部分を描けるのではないかと感じて。いわゆるお決まりの観光地、渋谷のスクランブル交差点とか、そういった場所だけではなく、もっと日本の根本的な、神話や場所の歴史にスポットライトを当てたイマーシブシアターを創ることで、海外の方にも関心を持っていただけるんじゃないかなと考えました」
近藤「私も同じ時期に『スリープ・ノー・モア』を観劇して、計り知れない衝撃を受けました。寝ても覚めてもその体験が忘れられなくて。また、ニューヨークで作品を観る前に、友達の結婚式に行ったのですが、立食のパーティ形式で、会場の方がピンチョスを配ってくれていたんですね。その時に、こんなに楽しい場なのだから、もっと踊りながら配っても良いのに、と思ったんです。私は学生の頃からダンスばかりして過ごしていたので、日常生活の中にダンスがあって。客席があって、その先のステージでダンスを踊っているという劇場体験より、もっと手前に感受性の豊かな世界が存在していると思っていたので、それがイマーシブシアターでは表現できるなと感じました」
−お二人のお話を聞いていると、今まで演劇やミュージカルに距離を感じていた方にも、イマーシブシアターは新たに興味を持ってもらえるきっかけになるのではと思えます。
竹島「それは凄く期待していますね。今、結構アートに対する垣根は下がってきていて、美術館に行く垣根は下がったけれど、劇場に行く垣根はあんまり下がってない気がするんです。劇場への入口は1個しかないよりも、多角的にある方が良いと思う。そのうちの1つになれたら嬉しいです」
−本作を上演した先、今後の展望を教えてください。
近藤「最終的に、世界に発信できる日本発のイマーシブシアターを創りたい、という思いは確固たる想いとして持っています。また『Anima』をきっかけに、自分が持っている資産や土地にも何か生まれるのではないかと感じて、お声がけを頂いたりですとか、劇場ではない場所が劇場になって、作品が生まれていくということが出来たら、面白い展開になっていくのではないかと思います」
竹島「あとは、名刺になる作品を作りたいということですね。今、創って残るものが多い中、舞台は創ったら消えてしまう。そこに価値はあるけれど、いつでも観にいけるものではないというのは難しいところです。だから小さい規模でもずっとやり続けることで、イマーシブシアターを観る機会を増やしたいと思っています。まだイマーシブシアターがどういったものなのかを知らない方も多い中で、私たちの作品にいつでもアクセスできる場所というのを創っていきたいです」

イマーシブシアター『Anima』は2023年12月9日(土)、10日(日)、16日(土)、17日(日)の4日間、BnA_WALLにて全16回上演。チケットの詳細は公式HPをご確認ください。

イマーシブシアターという名前はよく聞くけれど、まだ行ったことがない、1人で行くのは緊張するという方も多いかと思いますが、daisydozeは誘導型なので、安心して身を任せることができますね。