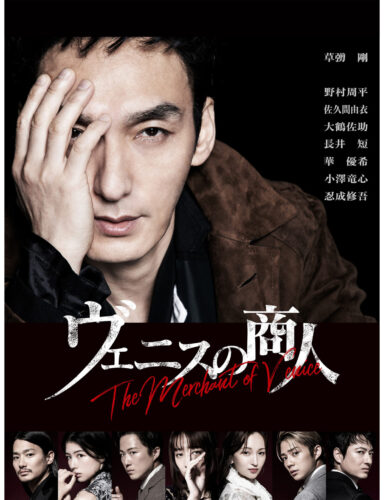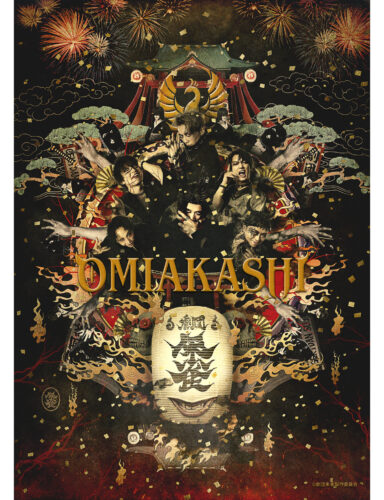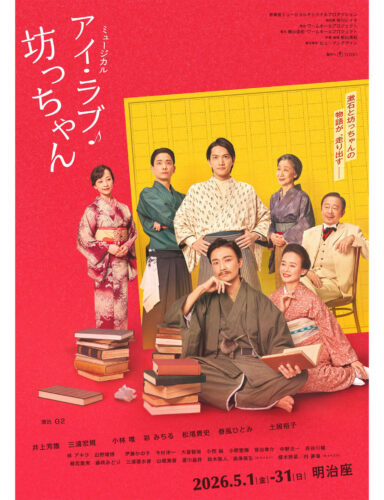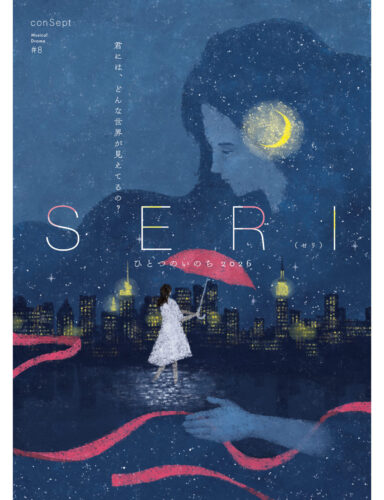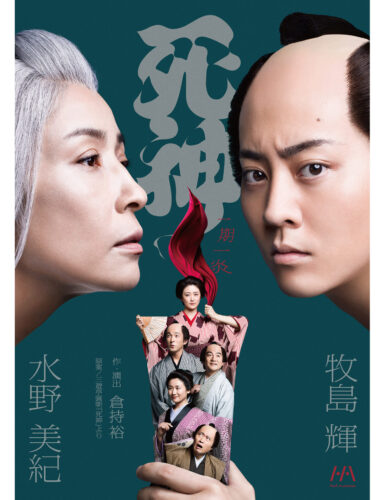『屋根の上のヴァイオリン弾き』は1964年にブロードウェイで初演され、演劇界の最高峰トニー賞ミュージカル部門において7つの賞を受賞した名作です。
2025年3月7日(金)〜29日(土)まで、東京・明治座で市村正親さん、鳳蘭さんほか豪華キャストによる上演が行われます。本公演は東京のほか、4月5日(土)の富山公演を皮切りに、愛知、静岡、大阪、広島、福岡、宮城、埼玉の8府県をめぐる全国ツアーが予定されています。
日本初演から半世紀以上が経つ現在も多くの人々に愛され続けているこの作品。その背景にある歴史と時代性を紐解きます。
『屋根の上のヴァイオリン弾き』あらすじは?|伝統と変化を描く名作
『屋根の上のヴァイオリン弾き』の舞台は、1905年の帝政ロシア、アナテフカという寒村です。
酪農業を営むテヴィエは、信心深くてお人好し。妻のゴールデには頭が上がらず、楽天家で働き者の市民です。
テヴィエとゴールデには、長女のツァイテル、次女のホーデル、三女のチャヴァなど5人の娘たちがいます。特に年頃の娘たちは、自分たちの結婚について日々関心が高まっている様子です。
ある日、金持ちの肉屋、ラザールからツァイテルを後妻に迎えたいという申し出がありました。テヴィエは酔った勢いで、この結婚に同意してしまいます。しかし、ツァイテルには、仕立て屋のモーテルという相思相愛の男性がいたのです。
ユダヤ教のしきたりには、両親の祝福がなければ結婚が許されないという厳格な決まりがありました。テヴィエは苦悩するものの、ついにツァイテルとモーテルの結婚を許します。
やがて、次女ホーデルは革命を志す学生・パーチックを追ってシベリアへ、三女のチャヴァもロシア人学生のフョートカと駆け落ち同然で家を飛び出してしまいます。
娘たちは次々に親元を離れ、やがてテヴィエ一家にも故郷を追われる日が迫っていたのでした。
原作は『牛乳屋テヴィエ』|反ユダヤ主義時代に書かれた小説
『屋根の上のヴァイオリン弾き』の原作は、ショレム・アレイヘムによる『牛乳屋テヴィエ』という小説です。
ミュージカルと同じく、ユダヤ人のテヴィエ一家を主人公としています。
先述の通り、ユダヤ教には「両親の祝福が泣ければ結婚が許されない」という決まりがあったものの、娘たちは異教徒の青年や革命家など、テヴィエが戸惑うような結婚相手を選び、親元を離れていきます。
ユダヤ人集落(シュテートル)のしきたりを破って新しい世界へと飛び出していく娘たちの姿に、この物語の主題である「民族離散(ディアスボラ)」を重ねた、イディッシュ文学の金字塔として知られています。
作者のショレム・アレイヘム(1859-1916)はキエフ近郊で生まれたユダヤ人の作家です。ロシアによるユダヤ人同化政策が進んでいた時代に生きるなかで、アレイヘムもロシアの教養を兼ね備えたユダヤ人として成長していくことになりました。裕福な家庭で育ち、家庭教師の仕事をしながら家庭を持ちますが、その頃ロシアでは反ユダヤ主義の圧力が強まっていきます。
そのような時代背景から、アレイヘムは母語である「イディッシュ語」を自分にふさわしい表現方法として考えるようになりました。そして彼は生涯を通して、イディッシュ語で書かれた多くの文学作品を生み出したのです。
作品の舞台となった時代|急変するユダヤ人社会
それでは、『屋根の上のヴァイオリン弾き』が書かれた時代のユダヤ人たちは、どのように暮らしていたのでしょうか。
ショレム・アレイヘム作、西 成彦訳『牛乳屋テヴィエ』(岩波書店)によれば、分断によってポーランド王国が消滅した18世紀末からあと、それまでポーランドに住んでいた大半のユダヤ人たちはロシア帝国の支配下に置かれることになりました。テヴィエたちも、そういったユダヤ人の一員だったのです。
本作の執筆が始まった1897年頃には、当時のワルシャワ(ロシア領ポーランド)、オデッサ(ウクライナ)などにはユダヤ人の人口が全体の30%を超えていたということですから、かなりの数のユダヤ人がいたことになります。
しかし先述の通り、その頃ロシア国内では反ユダヤ主義の考えが高まっていました。その動きは次第に加熱し、20世紀初頭には「ポグロム(ユダヤ人襲撃)」が起こります。
同じ頃に、12歳の少年への殺人容疑でユダヤ人が逮捕された「ベイリス事件」が起こりました。実際は冤罪だったのですが、この事件の背景にも反ユダヤ主義が関係していたと言われています。
作品の先にある未来|ナチスによる迫害
やがて20世紀中ほどの1940年代にはドイツのアドルフ・ヒトラーによる“ナチス政権”によって、主にユダヤ人を対象とした大量虐殺や迫害が起こります。ヒトラーは、当時のドイツの経済・政治面の悲惨な状況が起こったのはユダヤ人のせいだとして、彼らを強制収容所へ送り、虐殺を繰り返しました。
ナチス政権によって虐殺されたユダヤ人は600万人を越えるといわれています。ほかにもポーランド人を筆頭とするスラブ系民族や遊牧民族のロマ、捕虜軍など約500万人の人々がナチスによって虐殺されました。この被害はウクライナ方面に住むユダヤ人にも及び、ユダヤ人集落の無人化が進んでいきました。
これらは『屋根の上のヴァイオリン弾き』の時代からは少し先の話になりますが、作中にもすでにユダヤ人迫害の様子が描かれています。
前述の岩波文庫『牛乳屋テヴィエ』の巻末解説には「ウクライナのユダヤ人にとって『古きよき』時代の最終段階ともいえるのが、この小説の背景となった時代である」と解説されています。
激動の時代を生きたテヴィエ一家
『屋根の上のヴァイオリン弾き』の最後には、巡査部長がロシア皇帝からの命令として、テユダヤ人コミュニティ全体の立ち退きを言いつけます。そしてついにテヴィエ一家は、生まれ故郷アナテフカを離れ、アメリカへ移住することになるのでした。
「『古きよき』時代の最終段階」のなかで生き、伝統を大切にしながらも、日々を取り巻く変化に戸惑うテヴィエ。
ただ、『屋根の上のヴァイオリン弾き』では、時代の渦に飲み込まれてしまう悲しみだけではなく、家族の愛や新しい世界への旅立ちなど、いつの時代も人の心を打つ普遍的な感情が描かれています。
https://engeki-audience.com/article/detail/16842
『屋根の上のヴァイオリン弾き』は3月7日(金)から29日(土)まで明治座、その後全国8都市で順次上演。公式HPはこちら
参考書籍:ショレム・アレイヘム作、西 成彦訳『牛乳屋テヴィエ』(岩波書店)

長きにわたり愛される名作『屋根の上のヴァイオリン弾き』。世界中が揺れている今の時代に、この作品が上演され続ける意味は大きいと感じています。