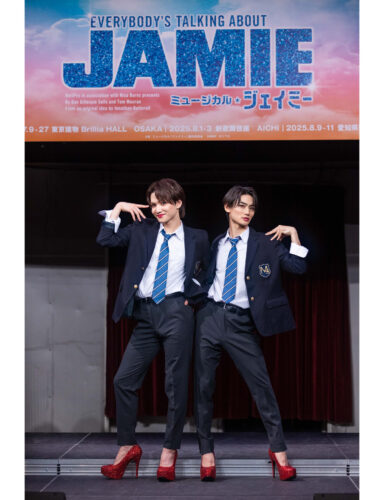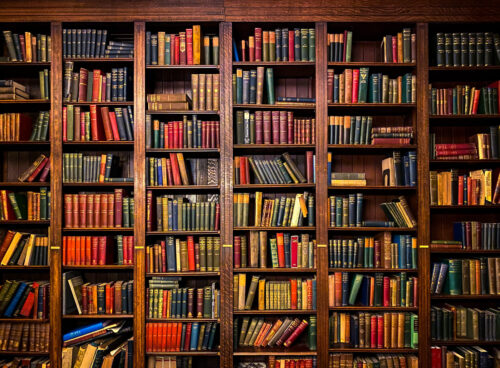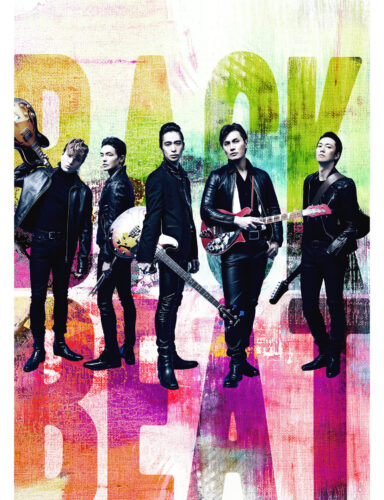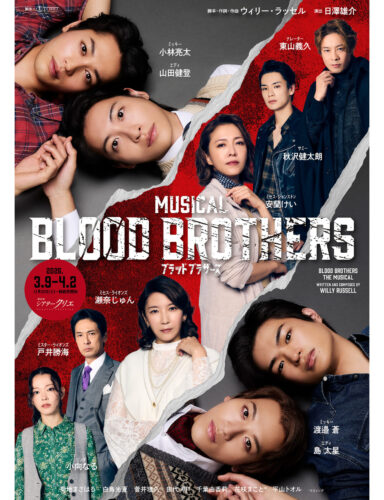ミュージカルといえば、歌とダンス、そして演劇が融合された、華やかな舞台芸術を思い浮かべる方も多いでしょう。では、「ストレートプレイ」とはどんな作品のことかわかりますか?本記事では、「芝居」や「演劇」とも言われるストレートプレイの意味や歴史、さらに日本や海外における上演の具体例を詳しくご紹介します。ミュージカルとは違った独自の魅力を知れば、きっと観劇の意欲が湧くはずです。
ストレートプレイはミュージカルとどう違う?
ミュージカルとは異なる「作品の構成」
ストレートプレイとミュージカルの違いには、大きく分けて「音楽」の存在があります。
ミュージカルやオペラなど、いわゆる「音楽劇」に分類される演目は、作品が「音楽」と「劇」で構成されています。
時代や観客に合わせて、音楽の要素が強い作品や演劇の要素が強い作品など、作風は変貌を繰り返してきました。
対して、ストレートプレイとは、音楽劇のように歌やダンスのない、科白(せりふ)をメインとして展開される演劇作品のことを指します。
音響効果として音楽が使用されることはありますが、ミュージカルやオペラのように、登場人物の気持ちを歌やダンスで表現することはありません。
ストレートプレイは一般的に「芝居」や「演劇」という言葉で知られており、「科白劇」や「正劇(せいげき)」という名称が使われることもあります。
表現の違いにより、「劇場の規模」が異なる場合も
また、ミュージカルやオペラが収容人数1000人以上の大きな劇場で上演されることが多いのに対し、ストレートプレイは100人単位などの比較的小さな劇場で上演されることもあります。
作中で歌やダンスが繰り広げられるミュージカルでは、群舞や合唱など大人数でのパフォーマンスが多く、広い舞台を必要とするためです。
一方、ストレートプレイでは、ミュージカルに比べると少人数の登場人物で展開する作品が多いのが特徴です。
また、科白や動作も私たちの日常に近いものが多く、小さな劇場でも上演できる特性を持っています。
日本でのストレートプレイの文化とは?その始まりから現代まで
日本におけるストレートプレイの歴史
『日本演劇史~明治から現代へ~』によれば、日本におけるストレートプレイを最初に上演したのは、川上音二郎(1864-1911)だと言われています。
彼はロンドンを皮切りにした、自身の一座の世界公演の後、帰国して「正劇」(科白劇)を日本に広めることを決意しました。
1903(明治36)年、川上は明治座でシェイクスピアの『オセロー』を上演し、これが日本初の正劇公演となりました。
当時の日本には、演劇で女性の役を演じる女優がいませんでした。しかし、『オセロー』のヒロイン・デズデモーナを演じたのは、川上の妻である貞奴(さだやっこ)でした。これを機に、日本国内で演劇に出演する「女優」の育成が始まることとなりました。
こうした川上の一連の取り組みは、演劇史において大きな転換点となり、「正劇運動」と呼ばれています。
日本のストレートプレイをけん引する「新国立劇場」
日本にも、イギリスと同じように上質なストレートプレイを上演し続ける劇場があります。
それは東京都・初台にある「新国立劇場」です。
新国立劇場は、演劇のほかに、オペラ、バレエ、ダンスなど現代舞台芸術のために作られた、日本唯一の劇場です。
同劇場では、主に中劇場と小劇場でストレートプレイが上演されます。
小劇場では作品によってさまざまな形態の劇空間を創造でき、中劇場では舞台を額縁のように仕切った「プロセニアム形式」、舞台を客席前方までせり出した「オープン形式」に変化させられるのです。
このことからわかるように、新国立劇場では、さまざまな演出方法や作風の作品を上演できることがわかります。
国内外を問わず、多くの演目を上演し続けている新国立劇場。
海外の国立劇団の招致公演や、日本の作家による新作公演の発表など、形式にとどまらずさまざまなラインナップを楽しめます。
さらに「こつこつプロジェクト Studio公演」と呼ばれる、1年間の創作過程の中で節目ごとに行う「試演形式」での作品の上演も行い、より質の高い作品を生み出すチャンスを広げています。
新国立劇場の2024/2025シーズンのラインアップはこちら
劇団四季の意外な一面も。創設の原点はストレートプレイだった
日本で最も有名なミュージカル劇団といえば、劇団四季の名前を思い浮かべる方も多いでしょう。
しかし劇団四季では、ミュージカルだけではなく、多くのストレートプレイが上演されています。
1953(昭和28)年に、故・浅利慶太さんにより劇団四季が創立された当初は、フランスの劇作家ジャン・アヌイによる『アルデール又は聖女』が上演されました。
その後もストレートプレイの上演が続き、劇団四季ではじめてブロードウェイミュージカルが上演されたのは1972(昭和47)年のことだったのです。
ミュージカルをメインに上演しているイメージが強い劇団四季ですが、そのラインアップには多くのストレートプレイが含まれています。
たとえばシェイクスピアの『ヴェニスの商人』や三島由紀夫の『鹿鳴館』など、さまざまなジャンルの作品が上演され、観客を楽しませました。
また、2025年11月からは、東京・浜松町にある「自由劇場」にて、若き日のシェイクスピアの恋を描いた『恋におちたシェイクスピア』が上演されます。本作品は2014年にイギリス・ウエストエンドで上演された舞台で、同名の映画はアカデミー賞で7部門を受賞した名作です。
劇団四季で上演されるストレートプレイを鑑賞したことがない方も、この機会にぜひご覧になってはいかがでしょうか。
『恋に落ちたシェイクスピア』劇団四季の公式HPはこちら
世界が認めるストレートプレイの殿堂。イギリスの「ナショナル・シアター」
世界で最も活気のある劇場、その実態とは?
世界で最も活気のある劇場と言われているのが、イギリスにある「ナショナル・シアター・オブ・グレートブリテン(英国国立劇場。以後、ナショナル・シアター)」です。
この劇場には、1100人を収容する「オリヴィエ劇場」、900人を収容する「リトルトン劇場」、上演空間を自在に変化できる300人収容の「コテスロー劇場」の3つの劇場があります。
イギリスの首都・ロンドンには劇場が多く、シェイクスピア作品を上演する「シェイクスピア・グローブシアター」や数々のミュージカルを上演する演劇街「ウエストエンド」などを有しています。
そのような名だたる劇場の中で、ロンドンの全劇場入場者数の3分の1を占めるのがナショナル・シアターなのです。このことから、国内外の人々がストレートプレイに強い興味を持っていることがわかります。
時代と国を超えたストレートプレイ。演目の選定にも注目
そんなナショナル・シアターでは、イギリス国内外問わず、世界中の優れた作品が上演されています。
一例をあげると
・シェイクスピアの『ハムレット』や『オセロー』(イギリス)
・チェーホフの『かもめ』や『ワーニャ』(ロシア)
・エウリピデスの『メディア』(ギリシャ悲劇)
・ハロルド・ピンターの『ヴァージニア・ウルフなんかこわくない』、アーサー・ミラーの『みんな我が子』(アメリカ)
など、作品の生まれた国や時代を問わないラインナップが印象的です。
日本でも観られる!「ナショナル・シアター・ライブ」の魅力って?
また、同劇場では、2009年から「ナショナル・シアター・ライブ(NTL)」という試みが行われています。
これはナショナル・シアターが厳選した舞台を各国の映画館で上演するプロジェクトで、現在では40ヶ国を超える地域で上演されています。
もちろん、日本でもナショナル・シアター・ライブを鑑賞することが可能です。
最新のラインアップはこちら

ストレートプレイは科白と動作のみで物語が進むため、俳優の演技力や演出家には高いスキルが求められます。しかしその分、直接的な感情表現と繊細なニュアンスが伝わるのが魅力です!