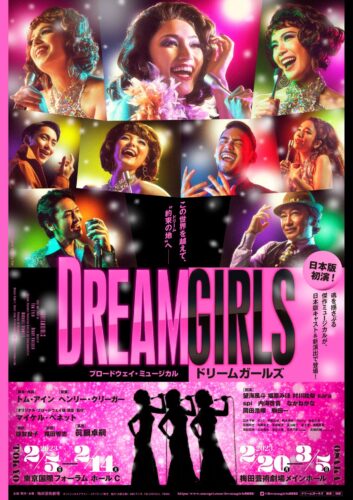帝政ロシア時代を生きるユダヤ人家族の悲喜を描いたブロードウェイミュージカル『屋根の上のヴァイオリン弾き』。世界中で愛されるこの名作は日本でも、1967年の初演から多くの人々の心を打ち続けてきました。
なかでも特筆すべきは、東欧の伝統的な音楽を取り入れた楽曲の数々。さらに、原作小説の『牛乳屋テヴィエ』からミュージカル『屋根の上のヴァイオリン弾き』が誕生するまでのドラマです。
今回は『屋根の上のヴァイオリン弾き』の代表曲や、作品の歴史を紹介します。
小説から演劇へ。原作者アレイヘムの挑戦
『牛乳屋テヴィエ』は、どのような歴史を経てミュージカル『屋根の上のヴァイオリン弾き』となったのでしょうか。
原作はいわゆるモノローグ形式の小説となっており、これを舞台化するにはいくつかの段階が踏まれていたことがわかります。
1914年、原作者のショレム・アレイヘムは結核を患いながらも、アメリカ・ニューヨークで『牛乳屋テヴィエ』の最後の二章の執筆と、同作品の劇場版を作成することに心血を注いでいました。
この原案をもとに、1919年には劇場版が完成し、モーリス・シュヴァルツが主演と演出を務めました。彼はのちに同作品の映画化を手がけることになりました。
1930年代に公開された映画版では、ショロム・セクンダが音楽を担当しています。彼は、日本でもよく知られている楽曲『ドナドナ』の作曲家でもあります。
1938年以降、演劇版『牛乳屋テヴィエ』は、モスクワに誕生した国立ユダヤ室内劇場で上演されることになります。この劇場は現存されていないものの、天井や壁、緞帳(どんちょう)などの設備すべてが、マルク・シャガール(1887〜1985)によって製作されていました。
アメリカで花開いた『屋根の上のヴァイオリン弾き』
1949年、アドルフ・ヒトラー率いるナチスによる大量虐殺や迫害によって、ロシア・東欧のユダヤ人社会は壊滅の危機を迎えていました。
そのような時代背景のなか、英語で読み書きを行うアメリカ系のユダヤ人たちに向けて、英語版の『牛乳屋テヴィエ』改め『テヴィエの娘たち』が刊行されました。
1950年代には『テヴィエの娘たち』の舞台化の試みを経て、ついに1964年にはブロードウェイミュージカル『屋根の上のヴァイオリン弾き』が上演されたのです。本作品は、約10年で3000回を超すロングランを記録しました。
『屋根の上のヴァイオリン弾き』というタイトルは、先述のシャガールの絵画「ヴァイオリン弾き」から命名されました。
シャガールの故郷である帝政ロシア下のユダヤ人コミュニティでは、婚礼や葬儀のときにヴァイオリン弾きらの楽師がユダヤの民族音楽を奏でていたことに由来しています。
“クレズマー”を世界に伝えるきっかけになった楽曲たち
東欧系ユダヤ人が奏でる音楽を、“クレズマー”と呼びます。
ヴァイオリンやクラリネットなどの悲哀を感じさせる旋律や、舞踊の快活さが特徴です。
『屋根の上のヴァイオリン弾き』の音楽を担当したジェリー・ボックは、ところどころにクレズマー風の旋律を組み込んでいます。伝統的な東欧の音楽がアメリカナイズされ、多くの人に知られるきっかけとなったのでした。
人生の喜びと切なさを描いた「サンセット・サンライズ」
『屋根の上のヴァイオリン弾き』の楽曲で最も知られているのが、『サンセット・サンライズ』。
娘の結婚式によせて、テヴィエ夫妻の喜びと驚き、そして寂しさの混じった感情が、美しい旋律に乗せられています。
メロディは哀愁を含みつつも、いつの間にか過ぎていく時の流れと、そのなかで営まれていく人生の趣深さが重なり、聴いている人の心をしみじみと打つのかもしれません。
特に「日は登り また沈み 時移る 喜び悲しみを乗せて 流れゆく」という歌詞が、いつの時代も変わることのない、愛や心の機微を表しているのではないでしょうか。
一見、家族の愛を歌った曲にも思えます。しかし著者には、もっと壮大なテーマも描かれているのでは、と感じられるのです。
3人の娘たちが歌う「マッチメイカー」
『サンセット・サンライズ』とはまた違った魅力を持つのが、テヴィエの娘たちであるツァイテル、ホーデル、チャヴァの3人が歌う「マッチメイカー」です。
自分の結婚について夢見る、年頃の娘たち。どんな結婚相手が理想なのか、まるでおしゃべりをするような軽快で可愛らしい楽曲です。
「みんなが羨む花嫁に あたしはなりたいの」「だけどハンサムだったら 文句は言わないわ」など、若い女の子の正直な気持ちが歌われており、とても微笑ましい曲です。
半世紀以上にもわたり、世界中の人たちから愛されてきた『屋根の上のヴァイオリン弾き』。
2025年3月からは市村正親さん、鳳蘭さんほか豪華出演者による公演が予定されています。東京公演は3月7日(金)から29日(土)まで明治座、その後全国8都市で順次上演。公式HPはこちら

東欧の伝統が息づくクレズマーの調べと、原作を受け継ぎながら進化を遂げてきた歴史。これらが重なり合い、『屋根の上のヴァイオリン弾き』は世代を超えた名作となったのではないでしょうか。