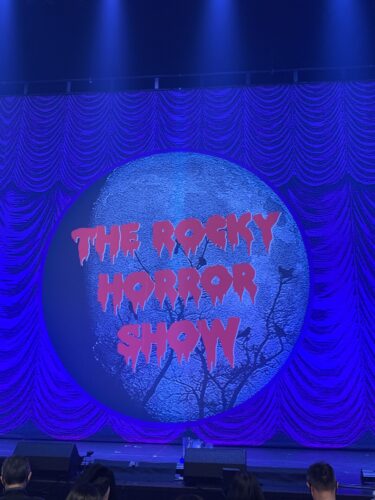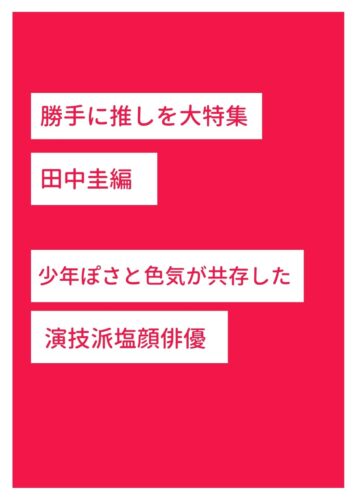ディズニーの『ライオンキング』は登場人物が全て動物というファンタジー要素たっぷりの作品です。その舞台版はアニメーションとはひと味違うキャラクター造形を取り入れ、世界的ヒットに繋がりました。今回はその象徴となる、動物を表現するパペットとマスクについてご紹介します。
演出家ジュリー・テイモアの感性 ーアイデアの源泉はアジアの伝統芸能にありー
ミュージカル『ライオンキング』を語るうえで最初に知っておきたいのは、演出家ジュリー・テイモアの独創性です。コスチュームデザインやパペットデザインにも携わった彼女がアジア圏の上演芸術にインスピレーションを受けて『ライオンキング』の世界観を築いたことは、すでにご存知の方も多いかもしれませんね。
ジュリー・テイモアは演劇を学んでいた学生時代、旅先のインドネシアで宗教儀式としての芝居に魅了され、そのまま数年間滞在して土着文化を吸収したという異色の経歴の持ち主です。テレビもない当時のインドネシアでは神に捧げる踊りや芝居が生活の一部として根付いていて、ジュリーは西洋の興行演劇にはない精神性に感化されたそう。現地での上演活動に勤しんだ彼女は庭に生えていた木を彫って芝居に使うマスクやパペットを作っていました。その後は日本を訪れて文楽や歌舞伎の手法を学び、アメリカに帰国。アジアで培った表現方法を演出作品に積極的に取り入れ、次第にその独創性が評価されるようになるのです。
パペット操作を芸術の域へ
さて、話題を再びパペットに戻すと、『ライオンキング』のパペット造形には、とりわけ文楽の手法が活かされています。文楽とは太夫、三味線、人形遣いが組み合わさった演芸で、ユネスコ無形文化遺産にも登録されている日本の伝統芸能のこと。ジュリーは1mにも満たない小さな人形を人形遣いが操作する文楽にヒントを得て、『ライオンキング』のパペットを構想しました。
4本の竹馬で四肢を伸ばし、長い首でバランスを取りながら悠々と舞台を横切るキリン。俳優に連動して動くよう繋がれたパペットの頭部と前脚を操作し、一心同体の動きが美しいチーター。台詞に合わせてパペットの表情までもコロコロ変わるサイチョウの家臣・ザズー。野生動物を表現しつつ、あえて操作する俳優の動きを見せるデザインによって、登場人物としての動物の存在と人形遣いの巧みな芸とを同時に体感できる仕組みになっています。パペット操作を完璧に習得するには、なんと2ヶ月以上もかかるそう。俳優が鍛錬を重ねてようやく吹き込まれる動物たちの息吹はまさに芸術の域です。
パペット操作の参考になるものがないかと探したところ、ディズニー・オン・ブロードウェイの公式YouTubeチャンネルにぴったりの動画を見つけました。舞台上に設置した360°アングルのカメラでブロードウェイ公演の「サークル・オブ・ライフ」の舞台上を覗けるという貴重な映像です。ほとんどの動物が登場するシーンですので、動物ごとに特徴的なパペットの動きと俳優自身の動きとをじっくり見ることができますよ。
ライオンを象徴するマスク
パペットが動物らしいフォルムを強調しているのに対して、メインキャラクターとなるライオンたちはマスクとアフリカの伝統的な柄を施した衣装で表現されています。俳優たちは大きなヘルメットを被るようにしてライオンの頭部を模したマスクを装着。こちらも、動物と演じる人間とを同時に見せたいジュリーの方針が貫かれ、マスクと俳優、2つの顔が見えるデザインです。
国王ムファサとその弟スカーのマスクは可動式になっていて、手元に仕込んだスイッチで操作する仕様。二人が口喧嘩をするシーンでは、マスクが俳優の顔の前にグンと下がった状態で向かい合い、まるで2匹のライオンが威嚇し合っているかのような緊迫感が漂います。このように、演技の決めどころでライオンらしさを特徴付ける手法は歌舞伎の立廻りや見得の影響を感じさせます。

ディズニーミュージカル『ライオンキング』はこれまで世界25のカンパニーが上演し、1億人以上を動員しています。西洋の美学にとらわれないジュリー・テイモアの手によって、アフリカの言語や伝統衣装とアジアの表現手法が編み合わされた、芸術性の高いミュージカル。父から子へ、百獣の王の威厳が受け継がれていくように、「サークル・オブ・ライフ(いのちの循環)」の物語はこれからも世界中に響き続けることでしょう。