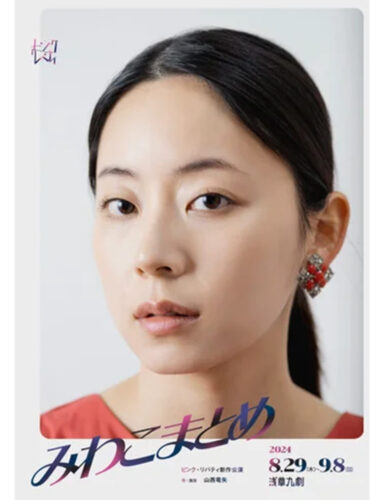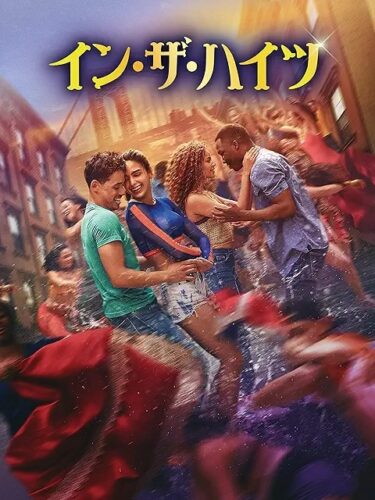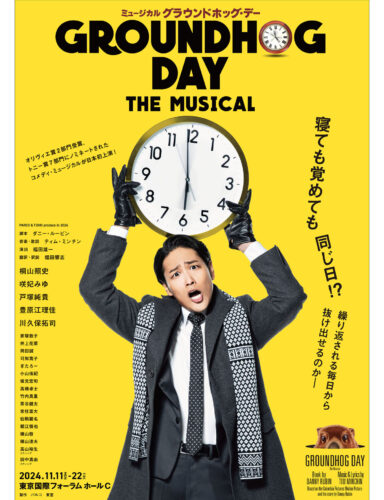師走になり、2022年も終わりが近づいて参りました。2022年に観劇した作品の中で、印象に残った作品『ザ・ウェルキン』と『夏の砂の上』の名シーンをご紹介します! ※作品に関するネタバレを含みます
女性たちの強さ、たくましさが描かれた『ザ・ウェルキン』衝撃のラストシーンに…
作品について詳しくはこちら。『ザ・ウェルキン』の舞台は1759年のイギリスの田舎町。1人の少女、サリー(大原櫻子さん)が殺人罪で絞首刑を宣告されます。しかし、彼女は妊娠を主張。妊娠している罪人は死刑を免れるのです。
そこで、真偽を確かめるために陪審員として、妊娠経験のある女性12人が集められます。多産の者、流産経験ばかりで子供のない者、早く帰って家事をしたい者など、生死を決める裁判への参加に戸惑う陪審員たち。
その中には、サリーに公正な扱いを受けさせようとする助産師のエリザベス(吉田羊さん)の姿がありました。サリーは本当に妊娠しているのか、そうでないとしたら、なぜエリザベスはサリーを庇おうとしているのでしょうか…。18世紀半ばの、男性支配社会に生きた女性たちの姿が浮き彫りにされます。
女性たちの強さ、たくましさが描かれている本作。最も印象的なのが物語最後のシーン。サリーは賄賂を受け取った下級公務員のクームスから暴行を受け流産してしまいます。いくら妊娠していたとはいえ、流産してしまえば、死刑は免れません。
当時の死刑は見世物でもありました。エリザベスは「一瞬だから」と説得しますが、サリーは「野次馬の前で死にたくない。少しでもまともに死にたい」と必死に訴えます。そんな彼女の様子に、覚悟を決めるエリザベス。
母という立場を超えて、同じ女性として、“シスターフッド”としてサリーに救いの手を差し伸べ続けたエリザベス。そんな彼女が、自分が産んだ子を自分の手で…と考えるだけで、計り知れない悲しみと、苦しみと、憤りを感じます。
そして、エリザベスに「彗星が見える」と言われ最後まで必死に彗星を探したサリーが、最期に見ることができた景色は何だったのか。犯罪を犯してしまった彼女は、何を思って生きてきたのか。
サリーとエリザベスだけでなく、11人の陪審員の女性たち一人一人についても大いに考えさせられた作品で、観劇後はしばらく席から動くことができないほどの衝撃を受けました。
観劇後も登場人物たちの生活を考えてしまう『夏の砂の上』
作品について詳しくはこちら。『夏の砂の上』の主人公小浦治(田中圭さん)は、長崎の田舎町で暮らしています。最近会社が倒産し、失業したばかり。しかも、妻・恵子(西田尚美さん)は治の元部下と不倫して家を出ていったのでした。
ある夏の日、妹の阿佐子(松岡依都美さん)が突然やって来ます。阿佐子は、借金返済のため福岡でスナックを開くと言い、娘の優子(山田杏奈さん)を半ば強制的に預けに来たのです。唐突に、叔父と姪の2人暮らしが始まります…。
幕が上がると、そこには茹だるような暑さの長崎での光景が広がっていました。世田谷パブリックシアターに組まれた、迫り出した舞台。ちゃぶ台と棚と扇風機しか置かれていない、畳の一室。その奥には廊下があり、さらにその奥には、2階に上がる階段があります。転換もなく、たったそれだけのシンプルな舞台セットなのに、長崎の坂の上に立つ小浦家での一夏を観客は感じることとなりました。
初めは自分の叔父である治と距離感を測っていた優子でしたが、一夏を過ごしていくうちに、叔父の痛みを知り、自分の痛みや弱さも見せるようになっていきます。
ほとんど雨の降らない長崎でのある日。雨が降っていると言って外にたらいを持って走り出る優子。たらいに溜めた雨を治と優子が交互に飲むシーンがあるのですが、2人の心が通い合っている様子が、色っぽくも美しく描かれているのが印象的でした。
優子が帰って1人になってからも治はちゃんと生活ができているだろうか、優子はまた治と長崎で過ごす機会はあったのだろうかと観劇後も、登場人物たちの生活が気になってしまうような、日常と地続きになっている舞台作品でした。

この2作品は、俳優はもちろん、戯曲がとても良かった作品でもあります。来年は日本版初上演のミュージカルが豊作の年なので、期待したいです!