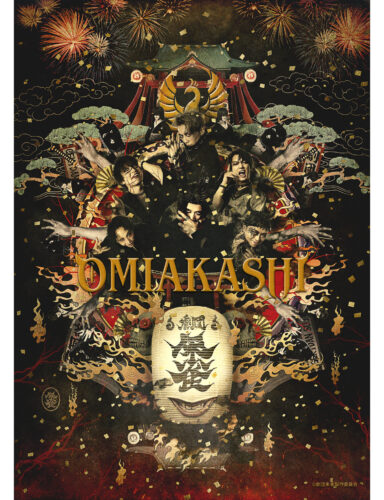数々のビッグタイトル作品が上演された3月、口コミで広がり、多くのミュージカルファンの心を掴んだ作品があります。韓国で制作され、日本初上陸を果たしたミュージカル『マリー・キュリー』です。ノーベル賞を2度も受賞した女性科学者の“ありえたかもしれない”物語に、胸が熱くなりました。(2023年3月・天王洲銀河劇場)※以降、ネタバレご注意ください
人種・性別のハードルを超えて、自分の“居場所”を探求していくマリー
マリー・キュリー、という名前を聞いて、すぐにピンと来ない人もいるかもしれません。少なくとも私の世代(30代)が小学生の頃に図書館にあった伝記で見た名前は「キュリー夫人」だったからです。脚本家チョン・セウンさんはまさにこの“誰かの奥さんである”本を娘が読んでいるという事実から、本作を創作することになったのだと言います。
マリー・キュリーが2度のノーベル賞を受賞するという大きな功績を残しながらも、ポーランド出身であること、女性であることで偏見や逆境が多く存在しました。男性しかいないソルボンヌ大学(パリ大学)で“なぜ女がいるんだ”と疎まれるシーンは、彼女の孤独さと、それでも孤独に立ち向かう、科学への思いの強さを感じさせます。そして彼女の姿勢に深く共感してしまうのは、勉強するのが好きだと語ると物珍しい顔で見られ、時には“女性は賢くない方がモテる”と囁かれることが今でもあるからなのです。
マリーには大きな夢がありました。まだ当時見つけられていなかった元素を見つけ、空欄になっている元素表を埋めること。科学に詳しくない人間にはその興奮が分かりにくいものですが、それを彼女自身の境遇と照らし合わせ、“居場所を見つける”旅路なのだと歌うことで、探求する物事は異なっていても、探究心のある人々なら誰もが共通する思いなのだと気付かされます。
世紀の発見はやがて、大きな悲劇へ
彼女は夫や支援者の協力を得てポロニウムとラジウム、2つの放射性元素を発見しますが、ラジウム工場では体調を崩す人々が出始めます。史実ではマリーは放射線の危険性を認めなかったようですが、本作では共に夢を語り合った友人・アンヌが工場で働いていたことから、その事実に苦悩するようになります。
一度危険性を認めてしまえば、可能性をも潰されてしまう。放射線によって不治の病であったガンの治療が行えるかもしれないのに、発見者自らが危険性を公表すれば、ガンから救えた患者を見捨てることにもなりかねない。ラジウムを自分の分身のように思っていた彼女にとって、それほど辛いことはなかったはずです。素晴らしい発明が、自分自身の居場所と共に見つけた宝物が、実は誰かを殺していたかもしれないなんて。
アンヌの存在や大きな味方であった夫ピエールの死を絡め、彼女の身を切るような思いを情緒的に描くのは、さすがの韓国ミュージカル。夫ピエールの大きく温かな愛情と、事故の隠蔽を責めながらも“マリーはラジウムじゃないよ”と救いの言葉を投げかけてくれるアンヌの強さは、涙なくしては見られません。
マリーの若い頃から死の直前までを豊かに演じた愛希れいかさんはもちろんのこと、ピエールを愛情たっぷりに演じた上山竜治さんと、アンヌを可愛らしくも力強く演じた清水くるみさんの存在こそが、本作を美しい作品へと仕上げ、多くの人の心を掴んだ理由ではないでしょうか。
2人の存在により、マリーはラジウム自体が自分なのではなく、ラジウムの特性を正確に捉え、伝えていくことが科学者としての自分であると気づくのです。
またマリーの支援者であり、放射能の危険性に気づきながらもラジウム工場を運営し続けるルーベンを演じた屋良朝幸さんは、持ち前のダンスを活かした表現方法でも他のキャラクターとの異質感を浮かび上がらせます。ルーベンのように、危険性を無視し、科学を商売に使う人間の卑しさが、やがて原爆を始めとする大きな悲劇に繋がってしまったのでしょう。
しかしそれはマリーの科学への探究心と、科学を正しい方向に活かそうとした思いとは全く異なるもの。科学の発展で変化してきた私たち人間は、いつでも誤った方法で科学を使うこともできる。それを常に自覚し、マリー、ピエール、アンヌのような大きく美しい夢を描ける人間でありたいと、強く感じました。
ミュージカル『マリー・キュリー』は4月20日から梅田芸術劇場シアター・ドラマシティにて大阪公演が上演予定です。

個人的に『エリザベート』の皇后暗殺者ルキーニのイメージが強かった上山竜治さんがとても愛情深い人物ピエールを演じられ、しかもルキーニもピエールもどちらもハマり役に感じたことに驚きました。本作のテーマの1つである女性としての視点はもちろんですが、原爆を経験しているという視点からも、日本で上演する意義を感じます。