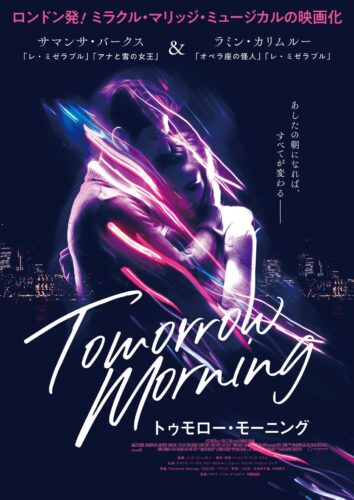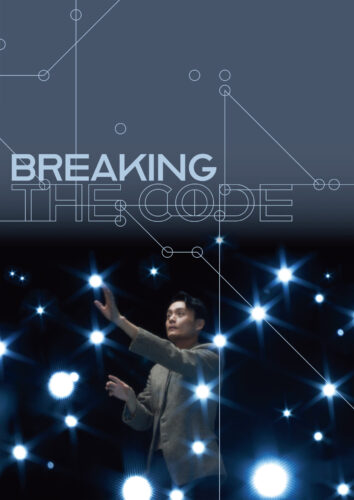実の父親が出演するなど、実体験や取材に基づいて作品を描いてきたゆうめい。新作『ハートランド』では駆け込み寺的なコミュニティでのフィクションを描きます。そして、海賊版の映画を制作していた“映画泥棒”的な役柄として相島一之さんが出演。相島さんから見たゆうめいの魅力、そして作・演出の池田さんが語る本作で描きたいものとは?
「テレビの向こうにいる存在」だからこそ出演をオファー
−まず、相島さんへのオファーの経緯を教えてください。
池田「今までゆうめいの作品は実体験を元に作ってきて、父親に出演してもらった作品もあります。そこから今回はフィクションを作りたいと思った時に、ゆうめいらしく、地続きの中のフィクションを描きたいと考えました。
実生活の中でフィクションに移行する場面を考えた時に浮かんだのが、家族で映画を観に行くシーン。中でも母親の好きな映画が『有頂天ホテル』など三谷幸喜さんの作品だったので、そこに出演されていた俳優さんに出ていただきたいと思ったんです。日常の先、テレビの向こうに広がる世界に存在する方にオファーをしてみたくて。
相島さんはまさにそういった数々の映画の名作に出てこられた人ですし、本作のキャラクターが相島さんにフィットするのではと感じて、オファーさせていただきました。でもまさか承諾いただけるとは思わなくてびっくりしました」

−このお話を聞いて、相島さんはオファーを受けられたのでしょうか?
相島「いえ、オファーを受けてから台本をいただいて、そこから初めて池田さんにお会いしたんです。オファーを頂いた時が舞台の本番中だったこともあって、時間があまりなくて。ゆうめいさんの作品を観たことはなかったのですが、今注目の劇団だということは聞いたことがあったので、実の両親が作品に関わっていることを知って、尖っているなぁと興味は持っていました。
私は常日頃から、若い才能のある人と出会いたいという思いが凄くあります。全ての役者は、才能のあるクリエイターと出会いたいと思っていると思います。そんな中で30代のクリエイターが声をかけてくれたことが嬉しかった。
30代の知り合いの俳優に“ゆうめいってどう思う?”と聞いてみたら、“相島さんが出たら面白いと思いますよ”と言ってもらったこともあって、オファーを受けることにしました。でもお受けした後もどうなるんだろうと正直ドキドキでした。台本を頂いたらとても面白かったので、ホッとしました」
“いずれ未来に起こるかもしれないこと”を描く
−実体験を描いてきたゆうめいの今までとは、異なるテイストの作品になりますか?
池田「今までとは違う作品ですが、根本の部分は変わらないと思います。これまでは過去にあった実体験をテーマにしてきましたが、今回は“いずれ未来に起こるかもしれないこと”を描くつもりです。映像を残すという映画と比べて、演劇ではリアルタイムに出来事が更新されていく意識が強いので、もしかしたら“未来に起こるかもしれない実体験”を、解像度を上げて描けたらと思いました」
−“未来に起こるかもしれない実体験”とは、本作の舞台になる山奥の駆け込み寺的なコミュニティのことでしょうか?
池田「そうですね。駆け込み寺というと田舎の原始的なイメージをすると思うのですが、この先果たしてそうだろうかと思います。本作を作るにあたって、題材になっているコミュニティがいくつかあるのですが、そこでのお話を聞いていると、独自の進化を遂げていると感じるんです。そこだけの独特なコミュニケーションがあったり、仕掛けがあったりする。
進化していくのは東京だけじゃなくて、東京で暮らしている日常では全然知らない進化が、別の場所で起こっている。そういったことを描きたいですね」

−相島さんは本作をどのように感じられましたか?
相島「まず、ミステリーであるということですね。作品に謎がいくつも散りばめられていて、ずっと最後まで引っ張っていく。池田さんは表層的な、日常的な会話を描かれるのですが、実はその奥にとてつもないものが隠されている。それがちょっとずつ出てくるので、上手くお客さんと共有しながら進めていく難しさを感じます。
でも台詞の端々に、今の世の中の生きにくさもリンクしてくる。さらにネットや最先端のテクノロジーといった要素も加わるので、とても異様な作品ですね。最後にお客さんにちょっとだけ前に進む希望のようなものが手渡せたらいいのかなと思っています」
池田「劇場に出て現実に向かっていく後押しというか、一方的に見ていた視点がほぐれていく瞬間を与えられたらいいなという思いはありますね。
例えば映画館で上映中にスマホの時間を確認しちゃう人っていると思うのですが、周囲へは迷惑だけれど、ある種、自分の時間を大事にしたという意味ではプラスでもあるのかもしれない。そこが現実とフィクションの差なのかなと捉えていて。ひどいことをされたと受け取るだけじゃなくて、もう一方に思考を変換してみると、自分のトラウマや生きづらさから離れた視点を見つけられる。それが今回ゆうめいで描きたいテーマです」
VRやAR…得体の知れないものが現実に介入する瞬間
−映像演出やモーションキャプチャーによるVR映像もあると伺いました。
池田「アバターのように、身体はここにあるけれど外の世界では別の形に映っていることで救われている人もいるので、そういったことも描けたらと思っています」
相島「テクノロジーとして最先端の状況を物語に落とし込んでいるなと感じますね。VRやAR、ネットなどの仮想の世界がリンクしていく…僕と同世代の方は理解するのが大変だとは思いますが、分かりやすく伝えたいです」

池田「メタバースとか、僕も正直よく分かっていなくて、でも日々単語が出てきて、知らぬ間に流行るものになっていくじゃないですか。得体の知れないものが現実に介入していく、得体の知れなさみたいなものも描けたらと思っています。演劇だったら生の目の前にある現実に介入する瞬間を描けるので」
−演劇だからこそ、という視点を凄くお持ちなのですね。
池田「様々な仕事をしている中で、最終的に“これは演劇に活かせるな”と思うんですよね。高校生の頃にチャットで見ず知らずの人と純愛小説を書こうとしたことがあったのですが、途中で荒らしにあって、どぎつい下ネタを入れられてしまって、一緒に書いていた人は今まで構築していたことを崩されたことに怒って出ていってしまったんです。僕はそれを見て凄くリアルだなと感じて、目の前で生身の人間がリアルタイムで物語を更新していくということに興味があります」
−相島さんが本作で伝えたいことはありますか?
相島「いつも思うのは、演劇の面白さが伝わったら僕は満足なんです。物語は作家さんによって色々とテイストが変わりますが、一様に“演劇って面白いぜ”ということは変わらない。それを伝えるために、僕は全力を尽くします。池田さんは新しい感性で、新しい演劇を立ち上げようとしている人だから、とても刺激になるし面白いです。参加できてよかったなと思っています」

ゆうめい『ハートランド』は4月20日(木)から東京芸術劇場 シアターイーストにて上演。チケットの詳細は公式HPをご確認ください。

演劇が“生”であるからこそ、できることを探索されている池田さんが描くフィクション。しかもVRやARが加わるということで、新時代だけど生々しい演劇、が見られそうです。