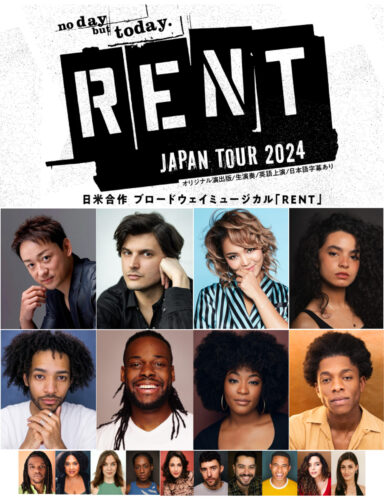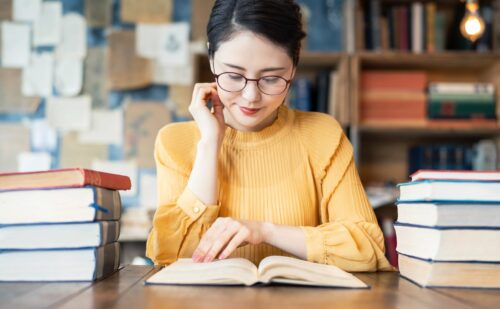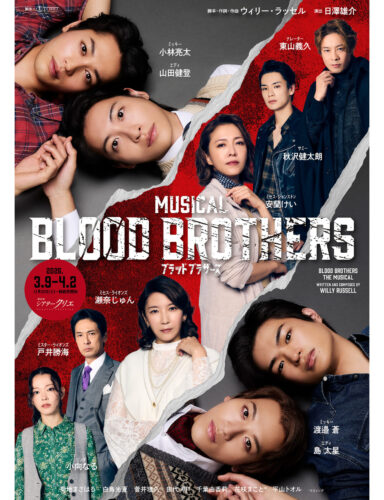野田秀樹さん率いる「NODA・MAP(野田地図)」の第27回公演『正三角関係』が、7月に開幕します。松本潤さん、長澤まさみさん、永山瑛太さんの豪華主要キャストも話題です。「NODA・MAP」は1993年10月に設立されました。旗揚げ公演が上演されたのが翌94年。その30年の歩みを改めてひもとき、過去のインタビューなどから野田ワールドのエッセンスを探っていきましょう。
人気絶頂の中での「夢の遊眠社」解散
野田さんは、東大在学中の1976年、所属していた「東京大学演劇研究会」から名を改め、劇団「夢の遊眠社」を旗揚げしました。ちなみに結成時の名称は、「おもしろくてためになる夢の遊眠社」でしたが、公演情報を載せた情報誌から「長すぎるから割愛する」と言われ、「夢の遊眠社」という名で定着していきました。
「ジャパン・アズ・ナンバーワン」として日本が経済大国に躍り出た1980年代、「夢の遊眠社」は、今で言う「倍速」の展開と飛び跳ねる身体、大がかりな舞台装置で、学生演劇の枠を超え、若者を中心に熱狂的な支持を集めました。野田さんは、劇団の主宰者、座付き作家、演出家、看板役者として八面六臂の活躍をしました。ワーグナーのオペラ『ニーベルングの指環』を下敷きにした『白夜の女騎士(ワルキューレ)』など3部作が1986年、代々木競技場第一体育館で一挙上演されると、1日に2万6,400人もの観客を集め、大きな評判となりました。しかし、劇団が大きくなればなるほど、それを維持するために公演を打つということが、野田さんには次第に負担になっていったそうです。
人気絶頂の1992年3月、「夢の遊眠社」は解散を発表、その秋の公演で17年間の活動に終止符を打ちました。公演回数は43回、総ステージ数1,205回、総観客数は81万2,790人を数えたそうです。解散公演を終えると、11月から野田さんは文化庁芸術家在外研修制度で英国・ロンドンに留学します。37歳秋の新たな旅立ちでした。
当時の心境について野田さん自身は、のちに東大の公開講座で次のように語っています。
「劇団をつくって6、7年もすると人気が出て、同時に経済的なバブルが始まった。(中略)そのまっただ中で夢の遊眠社という劇団は、おそらく徹底的に消費されていった。(中略)自分がやりたいことは、日本で消費されるために演劇を打つことでないなあ、と思い始めたんです。それで劇団をやめ、ロンドンに1年留学したんですね」(『日本の演劇人 野田秀樹』)
「NODA・MAP」をつくったロンドン
演劇の本場・ロンドンで、野田さんは芝居漬けの日々を送ります。ワークショップなどに積極的に参加して、遊びのように即興で演技をしたり、アイデアを出し合ったりする中で、演劇を志した原点を再確認したということです。
「ワークショップというのは、成功だけを目指すわけではなくて、探る作業なの。(中略)自分が演劇を最初に始めたのは(中略)たぶん探るためにやってきたわけね」(『MINERVA知の白熱講義② 野田秀樹×鎌田浩毅 劇空間を生きる 未来を予見するのは科学ではなく芸術だ』)
また、現地の演劇人たちの知己も得て、人脈を広げ、英国における芝居づくりの足がかりも得ました。
「ロンドンで新しい演劇の仲間と出会って、二十代はじめの姿にもどれたんですよ。二十代はじめに演劇の本当の姿がある」(『日本の演劇人 野田秀樹』)
1993年10月、野田さんは1年間の留学を終えて帰国すると、「NODA・MAP」を設立しました。公演の都度、俳優やスタッフを集めるプロデュース公演方式で芝居を打ち、ワークショップも開く企画制作会社です。留学中の野田さんが、ロンドンの地図を広げていた時に、その名前を思いついたということです。
野田さんは、留学時代の自分自身やあり得るべき役者の在り方について、古事記に登場する、体の皮をむかれて泣いている「因幡(いなば)の白兎」に繰り返し例えています。「因幡の白兎」となって海の向こうの本場の演劇界に渡った「ロンドン体験」が、その後の「NODA・MAP」の道標になったことを考えると、偶然ではないような気もします。
「NODA・MAP」は1994年1~3月、旗揚げ公演『キル』を上演しました。モンゴルの英雄テムジン(チンギスハン)の世界征服の野望を、ファッション界に置き換えて、愛と憎しみ、権力闘争を壮大なスケールで描く物語。タイトル「キル」には、「斬る」と「着る」、「生きる」の意味を含み、舞台となる「羊」の国は「洋服」に通じ、「糸さえ惜しい」は「いとおしい」、「ファッションショー」は「ファッショのショー」というように、言葉遊びも散りばめられています。
この旗揚げ公演から30年、「NODA・MAP」はほぼ毎年、芝居を打ってきました。上演史を振り返ると、先ほど紹介した『キル』をはじめ、中劇場規模の本公演は、2024年上演予定の『正三角関係』まで含めると、全部で27本。このうち新作は21本を数えます。作・演出を兼ねる人は多いのですが、野田さんはその多くに俳優として出演もしています。演劇に対する熱量とパワーに圧倒されます。舞台経験の豊富なベテランからフレッシュな俳優まで、アンサンブルという座組みを束ね、常連の顔触れのスタッフに支えられ、毎年話題作を送り出してきました。
一例を紹介すると、1999年初演の『パンドラの鐘』は、野田さん作の戯曲を、蜷川幸雄さんと野田さんがそれぞれ演出した作品が、都内の2劇場でほぼ同時期に上演され、話題をさらいました。パンドラの箱や蝶々夫人、道成寺伝説などのモチーフをちりばめ、太平洋戦争前夜、長崎で発掘された巨大な鐘を軸に、原爆や戦争責任の問題を浮かび上がらせた名作で、最近では、高校演劇などでも演じられています。
2019年初演の『Q:A Night at the Kabuki』では、英国ロックバンドQueenの名盤に乗って、シェイクスピアの悲劇『ロミオとジュリエット』と源平合戦を下敷きに、戦争に引き裂かれた男女の悲恋を切なく描き出しました。
古今東西の事物や古典、ニュース、社会的な出来事などの題材を換骨奪胎して、イメージの乱反射と笑いと美しい残像で眩惑させる野田ワールド。入り組んだ物語がらせん状に巡り巡って、私たち社会のありようを突きつける…。筆者自身、芝居を見終わった時、客席からなかなか立ち上がれないほどの衝撃を受けたことが何度もありました。
「演劇というのは『問い』であって、『答え』でない」(『野田秀樹×鎌田浩毅 劇空間を生きる』)という演劇観を信じる野田ワールドを観劇する時、筆者は理解しようとするのではなく、作品を全身で受け止め、かき乱されながら考え続けることでより深く味わえるような気がしています。毎年公演を楽しみに待つ観客の一人としては、野田作品を見ることで今の世界を知る座標軸になっています。
言葉遊びを封印、『THE BEE』の挑戦
こうした本公演のほかに、同い年の盟友、故・十八代目中村勘三郎さんと組んだ野田版歌舞伎も忘れられません。また、「夢の遊眠社」時代にはなかなかできなかったという、少人数・小空間の番外公演も、「NODA・MAP」結成以降の特色です。コロナ禍の時期を除いて、最近ではほぼ毎年のように海外公演を行っています。世界へ打って出るきっかけの一つになったのは、2006年6~7月にロンドンで初演した番外公演『THE BEE(蜂)』でしょう。
今でこそ野田作品の最高傑作の一つとされていますが、初演当時はその成否は当然ながら分かりませんでした。2003年にロンドンで上演した『RED DEMON(赤鬼)』は、翻訳を頼んだこともあり、作意が観客たちに十分に伝わらなかったところがあったと言います。そこで、『THE BEE』では、野田さんがアイルランド出身の劇作家と組んで、筒井康隆さんの原作小説『毟(むし)りあい』を基に英語で初めて台本を書き下ろし、英国の演劇人たちとの共同作業を重ね、ロンドンで一から作り上げた挑戦作でした。脱獄囚によって妻子を人質にされたビジネスマンが、解放交渉のために脱獄囚の妻子を人質にとって立てこもり、両者の間で凄惨な報復の連鎖を繰り返されるストーリー。言葉遊びを抑制し、身体性と想像力に委ねた演出で真っ向勝負したのでした。
初日が始まる前には「今回評判が悪かったら、ロンドンはもう終わりだなあ、と思いながら一か八かだ、みたいな気持ちで出て行った」(『野田秀樹×鎌田浩毅 劇空間を生きる』)と言う野田さん。新聞の劇評で好評を得て、次第にチケットが完売していきました。ちょうどその頃、筆者は野田さんにインタビューする機会を得ました。客席数約150人の小劇場に併設されたバーで、「毎日チケットの売れ行きが気になって…。こんなの学生以来かな」と伺い、覚悟の一端を垣間見たような気がしました。「日本語を離れてもロンドンで受け入れられた。日本の現代演劇の質は低くないと、十分示すことができた」と、少し早口で話してくれたことを今でも鮮やかに覚えています。
「小劇場運動の旗手」と呼ばれた若い時代から、日本の演劇界をリードする立場になってからも、「因幡の白兎」となって、新たな挑戦を続ける野田さん。今度の新作ではどのような演劇の新しい地平を切り拓いてくれるのでしょうか。
関連記事:松本潤×長澤まさみ×永山瑛太で贈るNODA・MAP『正三角関係』東京・北九州・大阪・ロンドン公演決定
【参考文献】
『MINERVA知の白熱講義② 野田秀樹×鎌田浩毅 劇空間を生きる 未来を予見するのは科学ではなく芸術だ』野田 秀樹、鎌田浩毅・著 ミネルヴァ書房 2018年
『日本の演劇人 野田秀樹』 内田洋一・責任編集 白水社 2009年
『野田秀樹の演劇』 長谷部浩・著 河出書房新社 2014年
『劇談 ―現代演劇の潮流』 扇田昭彦・編 小学館 2001年
『だから演劇は面白い! 「好き」をビジネスに変えたプロデューサーの仕事力』 北村明子 小学館 2009年

今度の『正三角関係』もロンドン公演が予定されています。現地でどう受け止められるのか、注目しています。