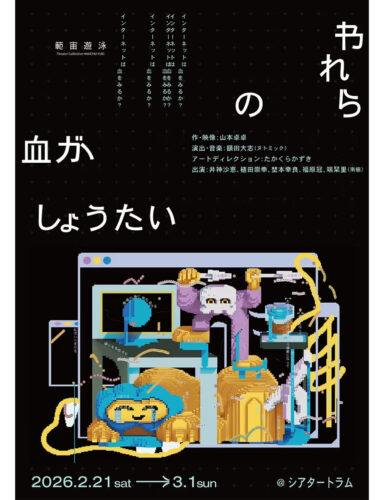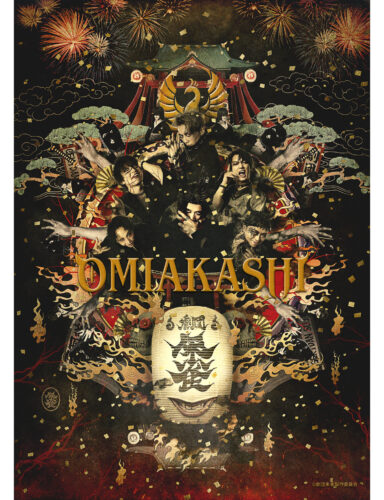ミュージカルの歴史は、1900年代初頭のアメリカ・ブロードウェイから始まり、現代に至るまで世界中で進化を遂げてきました。オペラやオペレッタをルーツに、時代ごとの社会背景や音楽スタイルを取り入れながら、数々の名作が誕生しています。本記事では、20世紀初頭から現在までの代表的なミュージカル作品と、その歴史的背景を時系列でわかりやすく解説。『ショー・ボート』『ウエスト・サイド・ストーリー』『レ・ミゼラブル』『ハミルトン』などの名作とともに、ミュージカルの進化の軌跡を辿ります。ミュージカル初心者からミュージカルファンまで、観劇をもっと楽しむための基礎知識として、ぜひご覧ください。
1900年代|オペラやオペレッタから派生した新しい芸術
ミュージカルという舞台芸術が生まれたのは、20世紀初頭のアメリカでした。
本格的なミュージカル作品の始動は1920年代だと言われていますが、それまでにもダンス主体の「レヴュー」と呼ばれる舞台芸術が存在し、さまざまな形を変えて、現在の「ミュージカル」と呼ばれる形態に変化していきました。
ミュージカルの前身は、ヨーロッパで長く上演され続けていた「オペラ」や「オペレッタ」です。
オペラは独唱や重唱、そして合唱に分類される歌と、オーケストラによる演奏によって、貴族の娯楽として楽しまれてきました。
その後、オペラをよりカジュアルに、短い上演時間へと改変したのがオペレッタです。オペレッタの観客は貴族ではなく、庶民たちでした。オペラ、オペレッタともにクラシック音楽で構成されています。
やがてオペラやオペレッタはアメリカへと渡り、当時流行していた歌や踊り、手品、寸劇などが披露される「ヴォードビル」といった娯楽文化と融合し、舞台芸術として発展していきます。
さまざまな舞台芸術が融合し、やがてミュージカルというひとつのジャンルが誕生したのでした。
1920年代から1930年代|「ミュージカルの時代」の始まり
1920年代には、ミュージカルの歴史を変えたと言われる重要な作品が誕生しました。
それは、作詞家であり脚本家であるオスカー・ハマースタイン2世(1895-1960)が作曲家のジェローム・カーン(1885-1945)とタッグを組んで生み出した『ショー・ボート』です。
本作は今までのミュージカルとは大きく異なるストーリーでした。それまでのミュージカルには、複雑でドラマチックなストーリーよりも、気楽に楽しめるハッピーエンドの方が多かったのです。
ところが、本作品では、当時では描かれてこなかった「人種問題」や「アルコール中毒」といった、センシティブなテーマを題材としました。諸説ありますが「『ショー・ボート』が生まれたことでミュージカルの時代が始まった」とも言われています。
しかし、1920年代の終わりにニューヨークの株価が大暴落し、「世界恐慌」が起こったことで、世界中の景気が悪化。ミュージカル界も不景気の影響を受け、1930年代には低迷期を迎えることになりました。
1940年|演劇賞とロジャース&ハマースタイン
1940年代前半は、第二次世界大戦の時代でした。当時のアメリカは、ヨーロッパの戦線へ向かう兵士たちの渡航拠点となっており、多くの人がブロードウェイを訪れたと言われています。
このことで、ミュージカルの聖地であるブロードウェイの存在が、世界的に広く知られるようになりました。
第二次世界大戦の影響を受け、ミュージカル作品にも兵士や戦時下の現実を描いた作品が多く作られました。1944年の『オン・ザ・タウン』、1949年の『南太平洋』など、戦線へ向かう兵士たちをターゲットとした作品が誕生しています。
また、ミュージカルの作品が洗練され、大きな進化が生まれました。
「台本ミュージカル」というジャンルが確立されつつあった頃で、それまでにない心理的な主題や、小説を舞台化するなど、脚本にも重きを置いた作品の製作が行われたのが特徴です。
さらに、1949年には、アメリカ演劇・ミュージカルの最高栄誉である「トニー賞」が設立されました。演劇賞が創設されたことにより、ミュージカル作品は新しい観客層を獲得していきます。
そして、1940年代のミュージカル界を語る上で欠かせないのが、のちに「20世紀最高のミュージカルの作詞作曲家コンビ」として知られることになる、オスカー・ハマースタイン2世と、作曲家のリチャード・ロジャース(1902-1979)です。
彼らが初めてタッグを組んだのは、1943年に初演を迎えた『オクラホマ!』でした。その後、1945年の『回転木馬』が、1949年には先述の『南太平洋』が上演され、次々に名作を発表していきました。
ふたりが作り上げたミュージカル作品は、トニー賞、グラミー賞、アカデミー賞、エミー賞、ピュリッツアー賞など、多くの名誉ある賞を受賞しています。このことからわかるように、ロジャース&ハマースタインのコンビは、ブロードウェイの第一人者としてその名を残しているのです。
1950年代|現在も愛され続ける名作ミュージカルの誕生
1950年代には、現在も愛される名作ミュージカルがたくさん登場しました。
この頃になると、1951年の『王様と私』、1956年の『マイ・フェア・レディ』、そして1959年の『サウンド・オブ・ミュージック』など、一度は耳にしたことのある作品名が並びます。これらの作品は、日本でも繰り返し上演されています。
『王様と私』、『サウンド・オブ・ミュージック』はロジャース&ハマースタインによって誕生しました。彼らは1940年代に続き、この時代にも多くの作品を残しています。
また、1957年には『ウエスト・サイド・ストーリー』も誕生しました。この作品では、当時ミュージカル作品で全盛期だった「タップダンス」を使わず、振付に「バレエ」を導入したことで大きな話題になりました。
シェイクスピアの『ロミオとジュリエット』を原作としたこのラブストーリーは、若者たちの恋愛模様だけではなく、移民問題や人種間の分断、また未成年の非行など、さまざまな社会問題が描かれています。
1960年代|「ロック・ミュージック」の登場と反戦への思い
1960年代後半からは、ミュージカルに「ロック・ミュージック」の要素が組み込まれていきます。この背景には、特に1960年代後半の若者文化が大きく影響していると言われています。
平和を求めて行動する「ヒッピー」と呼ばれる人々の登場によって、1967年には『ヘアー』というロックミュージカルが誕生しました。ヘアーとは「ヒッピー」の特徴である長い髪を指します。
初の本格的なロック・ミュージカル作品として評判を呼んだ本作は、当時行われていたヴェトナム戦争を背景に、反戦の声をロックに乗せて語った作品です。
出演者が客席に降りてきたり、通路を駆け抜けたりと、「ロック」にふさわしいエネルギッシュな演出が行われました。
そのほか、1965年の『ラ・マンチャの男』や1966年の『キャバレー』など、風刺的な作品も目立ちます。
また、1964年には『屋根の上のヴァイオリン弾き』が大ヒットし、3242公演という最長上演記録を更新しました。
1970年代|アンドリュー・ロイド・ウェバーが登場!リアルな姿を描いた作品も
1970年代には、イギリスからやってきた天才作曲家、アンドリュー・ロイド・ウェバーが登場します。
1971年には彼の作ったミュージカル『ジーザス・クライスト・スーパースター』によって、これまでの歌とセリフで進行するミュージカルから、全編が歌で進行する「歌いどおし」ミュージカルがポピュラー化しました。
この作品は、イエス・キリストの受難をロックミュージカルにした斬新なものでした。イエスやユダのキャラクターをあまりにも人間味溢れるものにしたため、宗教家から批判が起こったといいます。
また、『コーラス・ライン』は、実際にブロードウェイで踊るダンサーたちの生い立ちや境遇、ダンサーを志した理由などを脚本に反映させ、彼らのリアルな声を描いたことで話題になりました。
1980年代~90年代|『レミゼ』、ディズニーなど「メガ・ミュージカル」の誕生
数十年にわたり上演される「メガ・ミュージカル」
この時期になると、「メガ・ミュージカル」と呼ばれる作品が多く誕生しました。
これは、従来の観客層に加えて、ブロードウェイへの観光客をターゲットとした作品で、上演時からロングラン公演を狙って製作されたものです。
その代表格として、1982年ブロードウェイ初演の『キャッツ』(1981年ロンドン初演)、1987年のブロードウェイ初演『レ・ミゼラブル』(1985年ロンドン初演)や、1988年の『オペラ座の怪人』があげられます。また1991年には『ミス・サイゴン』(ロンドンでは1989年)が誕生しました。
これらの作品の共通点は、それまでのミュージカルにはなかった巨大な舞台装置です。
まるでオペラを思わせるような大きなセットが使われるようになったのが、この時代のミュージカルの特徴と言えるでしょう。
また、90年代には、ディズニーが自社作品をブロードウェイで舞台化したことも特筆すべき点です。1994年には『美女と野獣』が、そして1997年には『ライオン・キング』が上演されました。
『ライオン・キング』では、前衛芸術家として知られるジュリー・テイモアが演出を務め、話題になりました。彼女はライオンやハイエナ、鳥など動物のキャラクターを、仮面やパペット(人形)で表現し、多くの人の心を打ちました。この作品は、1998年のトニー賞で「最優秀ミュージカル賞」を受賞しています。
まだまだ続く、ヒットメーカーたちの新たな道のり
90年代には1992年にウィーン初演の『エリザベート』や1999年の『モーツァルト!』などで知られるミヒャエル・クンツェとシルヴェスター・リーヴァイが大活躍しました。
脚本と作詞を務めるクンツェと、作曲と編曲を担当するリーヴァイのタッグは、ドイツ発の「ドラマ・ミュージカル」という新たなジャンルを確立したのです。
彼らの生み出した数々の作品は、日本ではウィーンミュージカルの代名詞として知られています。
このように、80年代から90年代には多くのメガヒット・ミュージカルが誕生しましたが、近年でもその流れは続いています。
2015年にブロードウェイで初演された『ハミルトン』は、「米国建国の父」のひとりとして知られるアレキサンダー・ハミルトン(1755-1804)の生涯を描いた作品です。本作の脚本、作詞、作曲を担当したのは、映画『モアナと伝説の海』や『イン・ザ・ハイツ』などを手掛けたリン・マニュエル・ミランダです。
『ハミルトン』では、劇中でヒップホップが使用されたこと、実在する白人の役に非白人のキャストを起用した点など、異色の取り組みが行われました。これらが若者を中心に社会現象となり、大ヒットミュージカルに成長しました。
2000年代|懐かしさと新たなカルチャーの誕生
懐かしさと新しいドラマ性の融合へ
2000年代になると、懐かしのヒットソングをミュージカルにする「ジュークボックス・ミュージカル」が誕生しました。
これらの作品の特徴として、既成の有名曲を元に、新作のミュージカルを作るというスタイルが挙げられます。
たとえば、2001年の『マンマ・ミーア!』は、世界的なポップスグループ「ABBA」のナンバーで構成されたミュージカルです。本作は劇団四季によって日本でも繰り返し上演され、多くのファンがABBAの楽曲とハッピーなストーリーに心を奪われています。
また、2001年の映画『ムーラン・ルージュ』では、劇中に数々のヒットソングが使用されました。本作は2019年にレディー・ガガの「Bad Romance」やケイティ・ペリーの「Firework」など近年のヒットソングも盛り込んでブロードウェイで舞台化され、第74回トニー賞で10部門を受賞する快挙を成し遂げています。
そのほか、『ジャージー・ボーイズ』では、「君の瞳に恋してる」などで知られるボーカルグループ「フォー・シーズンズ」の楽曲が使われており、代表的な「ジュークボックス・ミュージカル」のひとつと言えるでしょう。
『マンマ・ミーア!』や『ムーラン・ルージュ』は、楽曲以外がオリジナルのストーリーでしたが、『ジャージー・ボーイズ』では、バンドグループの成功を夢見る登場人物たちの栄光と挫折が描かれています。ミュージカルでありながら、まるでドキュメンタリーを観ているような感覚になるかもしれません。
さらに、童話『オズの魔法使い』の前日譚をミュージカル化した『ウィキッド』が世界中で大ヒットし、2025年には映画版が日本で公開されるなど、ミュージカル界に旋風を巻き起こしました。
2000年代に世界へ躍進した韓国ミュージカル
2000年代に大きく花開いたのが、「韓国ミュージカル」です。
近年、日本国内ではK-POPや韓国文学など、さまざまな分野で韓国のカルチャーに触れられる機会が増えてきました。
多くの人を虜にする韓国のエンターテイメントの中でも、韓国のミュージカルに注目する方が多いようです。
韓国ミュージカルを語る上で欠かせないのが、韓国の演劇街として知られる「大学路(テハンノ)」です。70軒以上の劇場がひしめき、年間150本もの新作が上演されており、演劇文化が盛んであるとわかります。
大学路発のミュージカルで特筆すべきは、2005年に初演された『パルレ(洗濯)』です。主人公ナヨンを中心に、ソウルに住む人々の心温まる交流を描いた本作は、2012年に日本でも上演されました。
さらに、2025年7月からは、日本国内でも韓国ミュージカルを鑑賞できる「韓国ミュージカル ON SCREEN」が始まります。『エリザベート』や『モーツァルト!』など、日本でも人気の有名ミュージカル作品の映像を楽しむことができるのです。
一方、90年代から引き続き、ディズニー作品も人気を誇ります。
2000年の『アイーダ』や2008年の『リトル・マーメイド』など、大人も子どもも楽しめる作品が多く誕生し、新たな観客層を取り込みました。
2010年代|独自性が輝くフレンチミュージカル
ミュージカルの8割はイギリス、もしくはブロードウェイ発の作品と言われていますが、第3の流れとして注目すべきジャンルが誕生しました。それが、フレンチミュージカルです。
オペラ、オペレッタから派生し新しいジャンルを確立したアメリカ発のミュージカル作品や、ミュージカルに重厚な演劇要素を取り入れたイギリスのミュージカル。どちらとも異なる新しいスタイルを生み出したのが、フレンチミュージカルです。
その特徴として、演劇の要素よりもダンスや歌に力を入れ、従来のミュージカルよりもエンターテイメント要素を重視していることが挙げられます。
そしてもうひとつの特徴は、劇中の音楽に生演奏ではなく録音済みの音源を使用している点です。
これらの点から、アメリカ、イギリスで生まれた作品とは一線を画すスタイルが見受けられるのです。
フレンチミュージカルの代表的な作品は、2001年にフランスで初演され、2010年に宝塚歌劇団によって上演された『ロミオ&ジュリエット』です。翌2011年には「日本オリジナルバージョン」が上演され、ヒットを記録しています。
また、2012年にフランスで初演、2016年に日本版で初演を迎えた『1789 バスティーユの恋人たち』も、日本における代表的なフレンチミュージカルと言えるでしょう。本作は18世紀末、フランス革命が起こった激動の時代に飲み込まれていく主人公ロナンと、宮廷に仕える次女オランプの身分違いの恋を描いたラブストーリーです。
このように、ミュージカルの歴史を辿ってみると、世界の情勢や人々の需要によって、さまざまなスタイルの作品が誕生し続けてきたことがわかります。近年では、2018年に上演された『アナと雪の女王』で演出にプロジェクションマッピングを使用するなど、現代の技術を取り入れた作品も多くあります。
時代の変化とともに、これからも素晴らしいミュージカル作品が誕生し続けることでしょう。次回ミュージカルを観劇する際には、こうした歴史的背景に思いを馳せてみるのはいかがでしょうか。
【参考文献】
重木昭信 著『音楽劇の歴史 オペラ・オペレッタ・ミュージカル』(平凡社)
安部 寧 著『AII about 劇団四季レパートリー ミュージカル教室へようこそ![増補改訂版]』(日出出版)

有名なミュージカル作品を時代ごとに分けてみると、時代ごとの特色がくっきりと見えてきます。現在から「次の100年」のあいだには、ミュージカルはどのように変化していくのか楽しみです!