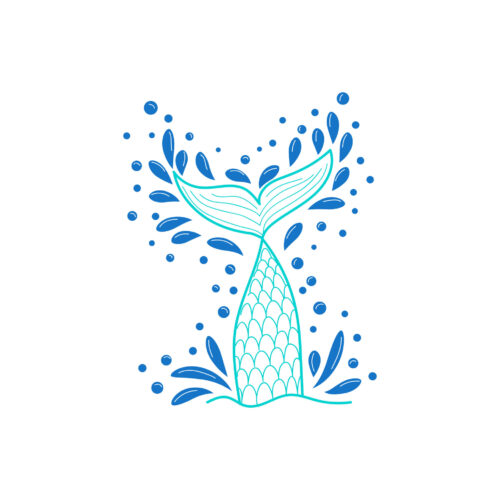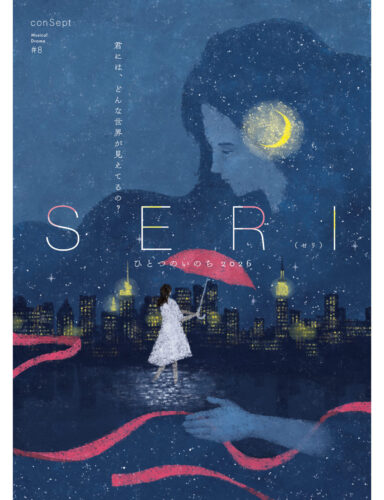ディズニー映画『メリー・ポピンズ』の舞台は1910年のロンドン。子供たちのしつけや身の回りの世話を担うナニーであるメリー・ポピンズがやってきたバンクス一家の様子には、階級社会や当時の情勢が垣間見えます。
バンクス家から見る、中流階級の暮らし
バンクス一家が暮らす家はこじんまりとしているものの、暮らし向きの良さが伺えます。料理人や使用人が仕え、誰も弾かないグランドピアノや数々の調度品が彩る華やかな生活。主人のバンクス氏は銀行役員であり、典型的なイギリス中流階級の暮らしの中でも豊かです。当時、裕福な家庭では住み込みのナニーを雇うのも当たり前のことでした。子供たちの世話やしつけはナニーに任せて、両親は子育てに関与せず、食事も別にしていたそうです。
バンクス氏は「The Life I Lead(私の暮らし)」で歌っているように、規律と伝統が大好き。子供たちは厳しくしつけ、妻は従順に、主人は絶対的な存在であらねばならない。映画で描かれる独りよがりなバンクス氏の態度は、伝統的な中流階級の美徳が染み付いてしまった父親像なのでしょう。メリーがやってくるまで、子供たちのいたずらに手を焼いて何人ものナニーが辞めてしまったという設定がありますが、両親の気を引きたいジェーンとマイケルのささやかな願いがいたずらに現れていることが感じられます。
世界経済を牽引する、斜陽の「大英帝国」
さて、中流階級のパパとして一家を支えるバンクス氏の勤め先は、ロンドンの金融街シティにあるドース・トームズ・モーズリー・グラブズ安全信託銀行。もちろん実在しない銀行ですが、手がける事業には当時のイギリス経済の興隆ぶりが感じられます。
19世紀、第二次産業革命と植民地支配で基盤を固め、大英帝国の名をとどろかせたイギリス。植民地では資源生産のための鉱山やプランテーションの開発、運送に必要な鉄道や運河の整備など、大規模なプロジェクトが次々に実施されました。開発資金を募って利益を還元する金融商品も増え、ロンドンは世界経済の中心として安定した地位を築きます。バンクス氏がジェーンとマイケルを連れて銀行にやってきた日に頭取のドース・シニアが歌う「Fedelity Fiduciary Bank(信用第一の銀行)」の歌詞にも、アフリカの鉄道、ナイル川のダム、紅茶のプランテーションなど、植民地の開発事業が銀行の投資先として挙げられていますね。
その後1914年に始まる第一次世界大戦の影響を受け、金融の中心地はアメリカへ。産業の規模も縮小し、大英帝国はゆっくりと没落していきます。映画の中で幅を利かせている銀行の取締役たちは揃って老齢。大英帝国の覇権もそう長くないことが暗示されているかのようです。
VOTES for WOMEN!女性の権利を訴えた活動家サフラジェット
映画の中でバンクス氏の妻ウィニフレッドは婦人参政権運動に終始夢中な様子。これは子育てに関与しないバンクス夫妻、という構図を強調するための映画独自の設定ではあるのですが、当時、実際に運動家として活躍していたのはウィニフレッドのような中流階級以上の女性たちでした。
19世紀を通して、イギリスの女性は「家庭の天使」として良き妻、良き母であることを求められました。男性に従順な女性像が理想とされ、家庭の外は男性の領分とする社会。そこに異を唱え、女性の社会的権利や参政権を求めて戦う女性グループが次々に登場します。参政権を意味するサフラジーという言葉から、活動家たちはサフラジストと呼ばれるようになりました。
何年も成果が出ない状況にしびれを切らしたエメリン・パンクハーストという活動家は器物損壊などの過激な手段に出ます。彼女が1903年に立ち上げたグループは投石や爆破事件を起こして収監されることもありました。その様子を皮肉った新聞記者が過激な活動グループをサフラジェットと表現したのです。
「Sister Suffragette(古い鎖を断ち切って)」をいきいきと歌うウィニフレッドもどうやら乱暴な手を使っている様子。首相の馬車に体をくくりつけた同志を称えたり、首相に投げるための腐った卵を用意したりしています。物語の本筋とは関係のないセリフの中に、彼女が熱中する集会の過激さを想像することができます。


筆者が初めて鑑賞した時は、楽しいミュージカルに心が浮かれ立つ一方、日本人には馴染みがないナニー任せの子育てや階級社会の美徳など、観ていて疑問に思うことがたくさんありました。他にも、煙突掃除人や階級ごとの訛りなど、本作にはイギリス社会を知る要素がいっぱいです。